
デューディリジェンス(DD)は、M&A成約間近の段階で行われる事前調査です。
譲受企業が譲渡企業に対して、税務や法務などの様々な角度から資産価値を測ります。
デューディリジェンスは、譲渡企業の「価値の適正確認」や「事前のリスク把握」に役立つため、譲受企業にとって非常に重要な工程です。
また、譲渡企業にとっても、最終的な譲渡価額に影響する可能性があるため、細心の注意を払って臨む必要があります。
本記事では、M&Aで重要なデューディリジェンスの概要や種類を紹介する他、一般的な流れや注意点も解説します。
目次
M&Aの過程で行うデューディリジェンス(DD)とは
デューディリジェンスとは、譲渡企業に対して企業の価値、将来の収益性、リスクの調査および分析を行う事前調査のことを指します。英語では「Due Diligence」と表記され、日本語では「適当かつ相当な調査」と訳されます。
デューディリジェンスでは、譲受企業が譲渡候補企業の経営環境や事業内容などの実態を財務・税務・法務などの様々な観点から調査し、資産価値を測ります。その結果を受け、譲受企業はM&Aのスキーム検討や譲渡価額の見直し、露見した問題への対処法取り決めなどを行うため、デューディリジェンスはM&Aの最終段階における重要な工程です。
デューディリジェンスの調査結果は、最終的な譲渡価額に影響を及ぼします。そのため、譲渡企業は自社の事業構造や内部統制についての詳細を再度把握するなど、入念な準備を行う必要があります。
▷関連記事:M&Aとは?M&Aの意味・流れ・手法など基本を分かりやすく解説

安田 亮
https://www.yasuda-cpa-office.com/
上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド
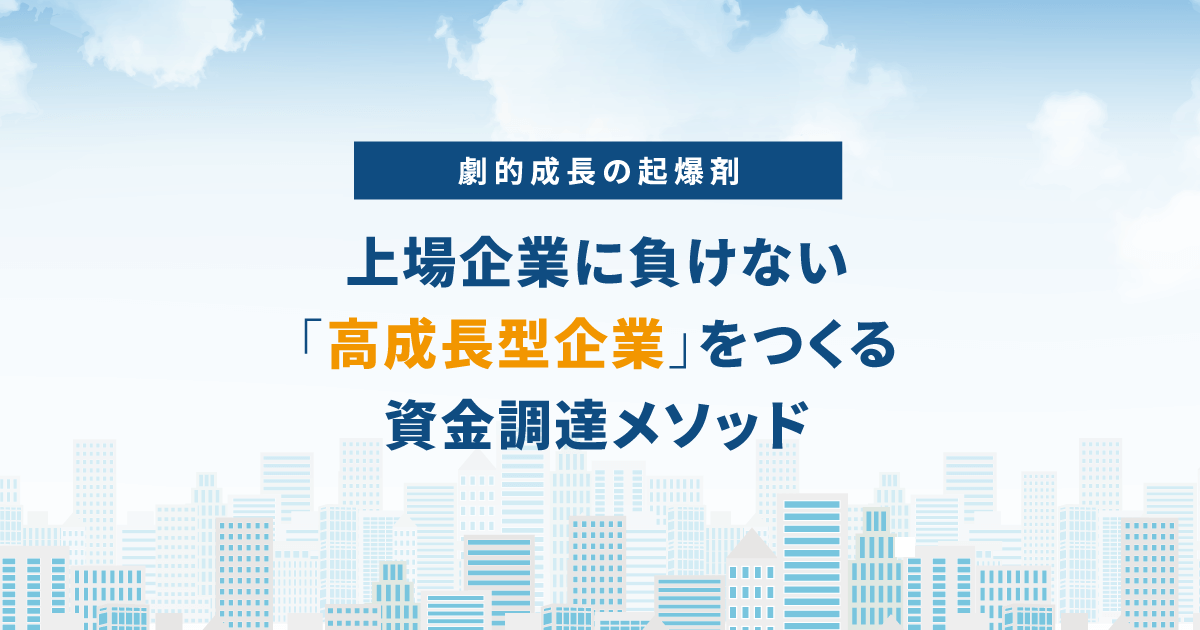
本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。
・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?
・まず必要な資金力を増強させる仕組み
・成長企業のM&A事例4選
M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。
デューディリジェンス(DD)の目的
デューディリジェンスを行う目的は、大きく分けると以下の5つです。
1. 企業価値の確認調査
2. ステークホルダーに対する説明責任
3. M&Aの手法の決定
4. リスクの把握・表面化した問題の契約書への反映
5. 統合後を見据えた情報収集
1.企業価値の確認調査
企業価値評価を行う際には、簿外債務が存在する可能性も含めて総合的に算定する必要があります。そのため、デューディリジェンスでは帳簿の内外を問わず、全ての情報を調査、分析します。
2.ステークホルダーに対する説明責任
徹底的な調査と客観的なデータ分析を行うことで、ステークホルダーに対してM&Aを行う定量的なメリットを説明できるようになります。
3.M&Aの手法の決定
デューディリジェンスを行った結果によっては、M&Aの手法を変更することがあります。
例えば、譲渡企業側が株式譲渡によるM&Aを希望していても、調査結果でリスクがあると判断された場合、株式譲渡ではなく事業譲渡に変更する可能性もあります。
そのため、譲渡企業について総合的に調査した後、両者にとって最も適切な手法を確定します。
4.リスクの把握・表面化した問題の契約書への反映
デューディリジェンスを行うことで、今まで見えていなかった問題が表面化することがあります。問題が露見した場合は、契約書の内容を修正し対応方法を取り決めます。
また、場合によってはM&A自体を中止しなければならない問題が見つかることもあります。
例えば、「譲渡企業が保有する技術・ノウハウの取得を目的にM&Aを検討していたにもかかわらず、期待する水準ではなかった」などの問題が発覚するなどです。
このように、デューディリジェンスを行うことで、M&A成約後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
5.統合後を見据えた情報収集
M&Aが成功するかどうかはM&A後に行われる二者間の統合作業(PMI)にかかっており、PMIの成功してはじめて、シナジー効果が最大限に発揮されたといえます。デューディリジェンスで客観的な情報を収集できれば、PMIの方向性を定めることが可能です。
譲受企業は、上記5つの目標を掲げてデューディリジェンスを実施しますが、最も重要なのは、「統合前の段階で企業間に存在する情報の非対称性の解消」と、「譲渡企業の価値やリスクの把握」です。デューディリジェンスによって正確に譲渡企業の経営実態を把握することで、解決すべき課題点を定量的に把握できます。
例えば、譲渡企業が不動産を保有している場合、時価や収益性を調査したうえで、そのまま保有するか手放すかを判断し、契約書への反映を検討します。また、実態に基づいて事業の優先順位をつけるケースも多いです。
このように、デューディリジェンスはM&A成約後の具体的な事業計画や将来性を測るだけでなく、調査で発覚した問題によってはM&A交渉の中断など、今後の意思決定に大きく影響する調査です。
▷関連記事:PMIとは?M&A成立後の統合プロセスについて実施期間や期待できる効果を解説
デューディリジェンス(DD)が行われるフェーズと期間
デューディリジェンスは、M&Aにおける成約までの流れの中で④基本合意フェーズの「基本合意契約の締結後」に行われ、コストや作業量を鑑みて調査項目を決定していきます。
| フェーズ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| M&Aの流れ | 相談 | 検討 | トップ面談 | 基本合意 | デューディリジェンス | 最終合意 | 最終契約締結・クロージング |
デューディリジェンスでは、数週間~数ヶ月(2週間〜2ヶ月ほど)の間に、専門家による調査とマネジメントインタビューが行われるのが一般的です。調査場所は、譲渡企業側の会議室などで行われるケースが多いです。
M&A成約の可否を分ける重要な調査であるため長い時間をかけて調査を行う印象もありますが、中小企業規模であれば、さほど時間がかからない場合もあります。
デューディリジェンスに臨む際は、スムーズな調査を行えるように、譲渡企業、譲受企業の双方が必要な資料を事前に揃えたうえで臨むようにしましょう。
デューディリジェンス(DD)の費用目安
前提として、デューディリジェンスにかかる費用は、一般的に譲受企業が支払います。また、かかる費用は対象とする企業や調査内容によって異なるため、明確な相場がありません。
費用は、依頼する専門家の経験やレベルによっても大きく変わります。弁護士や公認会計士、税理士などの専門家に依頼する場合は、費用が高額になる傾向があり、信頼できるレベルの高い専門家であればあるほど、それだけ費用も高額になります。
中小企業のデューディリジェンスでは、法務と財務、税務デューディリジェンスを行うことが一般的です。依頼内容や依頼する専門家によっても差がありますが、これらだけでも100万円~200万円以上の費用が必要です。状況に応じてその他のデューディリジェンスを加える場合は、さらに費用がかかります。
主な調査(事業・財務・法務・税務・人事・IT)の目安費用は、以下のとおりです。
| 調査の種類 | 1時間あたりの費用 | 総額 |
| 事業 | 2~10万円 | 30~300万円ほど |
| 財務 | 2~5万円 | 100~500万円ほど |
| 法務 | 2~5万円 | 70~200万円ほど |
| 税務 | 2~5万円 | 35~200万円ほど |
| 人事 | 2~5万円 | 44万円~ |
デューディリジェンス(DD)の種類
企業の実態を細かく調査するデューディリジェンスにおいて、その調査項目は多岐にわたります。
主要な項目は「事業」「財務」「税務」「法務」「人事」「IT」の6種類で、それぞれに専門的な知識が必要になる場面も多く、専門家(弁護士や公認会計士、税理士など)に依頼するケースが一般的です。
以下では、多くのM&Aの案件で行われるデューディリジェンスの項目を紹介します。
事業デューディリジェンス
事業デューディリジェンスとは、企業を包括する市場全体を鑑みたうえでの評価調査で、別名「ビジネスデューディリジェンス」とも呼ばれます。
市場における対象企業、つまり競合内での立ち位置などを確認したうえで、事業の将来性を見極め、経営計画の実現やM&Aの目的と適合しているかを調査します。
事業デューディリジェンスでは、以下のような内容を調査します。
・業界や市場などの譲渡企業を取り巻く環境
・特定企業への依存度
また、事業デューディリジェンスは、目的に応じて以下のように細分化されます。
・「売上」に注目する場合:コマーシャルデューディリジェンス(市場性の評価が目的)
・「内部環境」に注目する場合:オペレーションデューディリジェンス(買収後のコストやリスクの精査が目的)
▷関連記事:ビジネスデューディリジェンス(ビジネスDD)とは?目的や進め方について解説
財務デューディリジェンス
財務デューディリジェンスとは、財務的観点からの調査です。貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など主な財務諸表を基にして、対象企業の財政状態について調査し、将来的に期待できる収益性や、不正な取引や経理処理がないかなどのリスクを洗い出して確認します。
財務デューディリジェンスでは、以下のような内容を調査します。
・回収不能債権や貸倒懸念債権などの有無
・回収不能債権や貸倒懸念債権などの回収見込み額
・簿外債務の有無
・会計処理の適正性
▷関連記事:財務デューディリジェンス(財務DD)とは?目的や流れ、チェックリストを解説
税務デューディリジェンス
税務デューディリジェンスとは、M&A前の税務申告に関わるものと、M&A後にかかる税についての調査です。株式譲渡の場合、税務リスクを引き継ぐことになる譲受企業にとっては、特に重要なものとなります。
譲受企業が「申告漏れ」や「納税処理の誤り」などの事象を過去に犯し、そのことがM&A後に発覚した場合は、ペナルティが課され損失を被る場合があります。そのため、適正な申告や納税がされているかという調査は非常に詳細に行います。
税務デューディリジェンスでは、以下のような内容を調査します。
・決算報告書、税務申告書などの基本資料の調査
・申告漏れなどの税制上のリスク
・税務処理の適正性
▷関連記事:税務デューディリジェンス(税務DD)とは?目的やリスク、調査範囲について解説
法務デューディリジェンス
法務デューディリジェンスでは、譲渡企業が締結している事業関連の権利や債権・債務について、法務上の問題やリスクの有無を調査します。
法的リスクを抱えていると、訴訟が起きた際に莫大な時間とコストがかかってしまいます。また、企業への風評被害にも繋がり、経営に悪影響を及ぼす可能性があるため、入念に調査を行います。
法務デューディリジェンスでは、以下のような内容を調査します。
・法令遵守の確認
・営業・生産・人事などに関する訴訟リスクの確認
▷関連記事:法務デューディリジェンス(法務DD)とは?目的や費用、チェックリストを解説
人事デューディリジェンス
人事デューディリジェンスとは、人事制度やマネジメントの実態調査です。
従業員数や人件費だけではなく人事システムや労使関係など、労務に関する調査もこの中に含まれ、両者の人事制度や労働条件融合の際に活用されます。
また、人事デューディリジェンスの調査は、M&A後の組織再編においてとても重要です。経営融合前後の制度やマネジメントの相違における社員のモチベーション低下など、人事面のリスクを想定したうえで準備を整える必要があります。
人事デューディリジェンスでは、以下のような内容を調査します。
・組織・従業員の構成
・年金・退職金関連
・評価・報酬などを含めた人事制度
・福利厚生・雇用条件
▷関連記事:M&Aにおける人事の課題とは?人事デューディリジェンスや人事PMIを解説
ITデューディリジェンス
ITデューディリジェンスでは、譲渡企業が採用している情報管理システムの取り扱い方法を調査、分析します。既存システムとの融合における活用法や、それにかかる作業量やコストを考慮し、基幹業務に関するシステムをどのように結合すれば良いかを検討します。
M&A成約までの限られた時間で詳細かつ専門的な調査を行う必要があるため、実際には全項目の調査は行わず、特に中小企業では、事業、財務、税務、法務の4項目のデューディリジェンスを行うことが一般的です。
上記で説明したデューディリジェンスの項目と比べると、ITデューディリジェンスは主要な項目ではありませんが、下記のようなデューディリジェンスも実施される場合がありますので一例としてご紹介します。
環境デューディリジェンス
環境汚染のリスクや、それが発覚した際の企業の評判に及ぼす影響などを調査します。環境汚染への対応の懸念がある場合、多額のコストが見込まれるため、それに関連する事業を切り離す、もしくは企業価値を下げるという判断の基になる調査です。
知的財産デューディリジェンス
譲渡企業が特別なノウハウにより特許権やその他の産業財産権、著作権などを取得している場合、それらの価値調査、分析が行われます。
しかし、知的財産には形がないため、価値を測る評価基準はとても難しく、調査を専門家に依頼する必要があります。
顧客(カスタマー)デューディリジェンス
新規顧客と既存顧客の調査のことです。M&Aのデューディリジェンスで用いられることはそれほど多くありませんが、顧客の本人確認などを行い、マネーロンダリングなどの有無を調査するために実施するケースが一般的です。
不動産デューディリジェンス
譲渡企業が所有する不動産の分析と調査を指し、不動産鑑定業務ともいいます。不動産はデューディリジェンス時の周囲の環境や地価によって大きく変動するため、不動産鑑定士などによる分析、評価を行います。
M&Aにおけるデューディリジェンス(DD)の手順
では、デューディリジェンスは具体的にどのように行われるのでしょうか。以下では、一般的なデューディリジェンスの手順をご紹介します。
1. 事前準備(資料開示・事前分析)
2. 資料分析
3. マネジメントインタビュー
1. 準備(資料開示・事前分析)
デューディリジェンスの実施においては、譲受企業が譲渡企業に、M&Aに関わる資料開示請求を行い、譲渡企業は要請に応じた資料開示を行います。
譲受企業はあらかじめ調査すべき事業領域の絞り込みと計画を策定し、事業構造や内部統制の状況を把握します。また、譲渡企業の財政状況、市場面や顧客面など、様々な面から問題点を把握、抽出します。
譲渡企業と譲受企業間の秘密保持契約は、この段階で既に締結済みのため、情報漏洩のリスクは抑えられています。
▷関連記事:秘密保持契約書(NDA)-ひな形使用時の注意点 M&Aの情報漏洩対策のために
2. 資料分析
開示された資料を基に、融合において「シナジー効果はあるのか」「リスクはあるのか」などの視点で資料分析・把握作業が行われます。この分析は、譲渡価格の決定や契約書の作成に大きく影響します。
3. マネジメントインタビュー
マネジメントインタビューとは、譲渡企業のマネジメント層にヒアリングを行う作業です。インタビューでは、経営者の考え方や企業理念など書面では判断しにくい項目を直接質問することができ、より具体的に融合後のシナジーやリスクを可視化します。
これらの結果を踏まえて、契約書を作成していきます。
デューディリジェンス(DD)に関する注意点
最後に、デューディリジェンスを行ううえで譲渡企業が注意すべき点を解説します。
・チェックリストの事前活用
・実施するタイミング
・事前の計画立案
・情報漏洩のリスク
・マネジメントインタビュー対象者となった場合の準備
チェックリストの事前活用
それぞれのデューディリジェンスにおいては、ある程度標準化されたチェック項目があるため、その項目を基に調査や分析を行います。チェック項目は、自社の価値やリスクの把握などの事前チェックにも活用できます。
実施するタイミング
デューディリジェンスを実施するうえで最も注意しなければならないのは、タイミングです。一般的には基本合意契約締結後、最終条件の交渉前に行われますが、適切な実施タイミングを見極めることが大切です。
事前の計画立案
M&A成約までの限られた時間の中で、譲受企業が検討するうえで有効な情報を提出しなくてはなりません。計画的に重要なポイントを絞り、情報を把握しておくことが必要です。
情報漏洩のリスク
デューディリジェンスでは、譲渡企業の人事制度や財務状況などの様々な情報を入手します。一度情報が漏洩してしまうと取り返しのつかないことにもなりかねないため、情報の管理には十分な注意が必要です。
万が一、情報漏洩が生じた場合はM&Aの破談や契約違反による損害賠償などのリスクもあるため、徹底した情報管理が必要です。
マネジメントインタビュー対象者となった場合の準備
インタビューを受けるにあたり譲渡企業が事前に準備をしておくことで、より円滑に交渉が進みます。両者の関係性向上にも繋がるため、念入りな準備が大切です。
上記の内容に留意しますが、前提として譲渡企業は、デューディリジェンス前にM&A後に想定されるリスクなどを譲受企業に伝えておくことが重要です。デューディリジェンスの際に事前に知らされていない問題が発覚すると、M&Aの交渉に影響を与えます。
特に、譲渡企業が把握しているリスクを譲受企業に伝えていなかった場合、「譲渡企業は発覚した問題以外にも何か伝えていないことがあるのではないか」と譲受企業の不信感にも繋がってしまいます。
譲渡企業が譲受企業の調査を受ける際のポイント
デューディリジェンスを実際に行うのは譲受企業ではありますが、調査結果が最終的な譲渡価額にも影響を及ぼすため、譲渡企業は自社の事業や契約や決算書などについて詳細に把握しておく必要があります。
以下では、譲受企業によるデューディリジェンスで重要なポイントを説明します。
事前に個人と会社の関係を整理・分離しておく
譲渡企業は、デューディリジェンスのために多くの情報を譲受企業に伝える必要があります。例えば、会社の契約書は閲覧を要求されて提示することが多い文書の代表例です。
そのため、経営者が個人で譲渡企業と結んでいる契約書など、デューディリジェンスに必要な契約書を予め整理しておくと、調査が円滑に進むでしょう。
また、デューディリジェンスには現金出納帳や支払手形記入帳をはじめとする重要な決算書類が必要なため、その保管場所と記載内容を再度確認しておくことも大切です。譲渡企業は譲受企業にへの提出情報を確認し、事前に整理するなどの準備を行いましょう。
経理部門責任者や顧問税理士の協力を得る
中小規模の譲渡企業では、経営状況や財務を正確に把握できているのは経理部門責任者ということが多々あります。そのため、譲渡企業はこうした経理部門責任者や顧問税理士に事前に相談することで、予想される質問などに対して、スムーズに対応できるでしょう。
基本合意書に盛り込む内容はM&Aアドバイザーと相談する
基本合意書とは、M&Aの相手先企業との最終契約締結の前段階で交わされるM&Aの条件に関わりのある基本事項について定めた合意書です。その時点での合意事項について、両者の認識を合わせる目的で作成されます。
その後の取引をスムーズに進められるように、事前に専門家を交えて決定した取引条件について内容を盛り込みますが、一部の項目を除いて法的拘束力を持たせません。理由としては、その後に行うデューディリジェンスの結果やその後の状況で取引条件が変更になる可能性があるためです。
しかし、独占交渉権や秘密保持義務などは個別に法的な拘束力を定めている場合が一般的です。
どのような基本合意を締結しておけばその後の手続きが円滑になるのかということを、譲渡企業と譲受企業ともに、M&Aの経験が豊富なアドバイザーに相談しましょう。
▷関連記事:M&Aにおける契約書の内容とは?意向表明書や基本合意書についても解説!
譲受企業による企業価値評価で自社に対する考え方を知ることができる
M&Aでは、株式や事業の価値にのれん代を足して、譲渡価額を算出します。のれん代は、譲渡企業の持つブランドや技術力、社員の能力など、形に表せない非金銭的な資産を指します。
そのため、のれん代によって譲受企業が譲渡企業のどのような点を魅力と考えているのかを知ることができます。
例えば「譲渡企業の持つブランド力に魅力を感じているのか」「取引先や許認可などを評価しているのか」など、のれん代を通して把握することが可能です。
▷関連記事:M&Aの「のれん」とは?償却期間や会計処理、注意点を分かりやすく解説
まとめ
デューディリジェンスは、M&A成約まであと一歩の段階ですが、ここで判明した問題によりM&Aが破談することもあるため、M&Aの交渉において最大の難関といえます。
これまでの時間や努力を無駄にせずM&Aを成功させるためにも、譲渡企業は事前に想定される調査項目や内容について把握しておき、改善していくことが大切です。念入りな準備を行い、デューディリジェンスに備えましょう。
