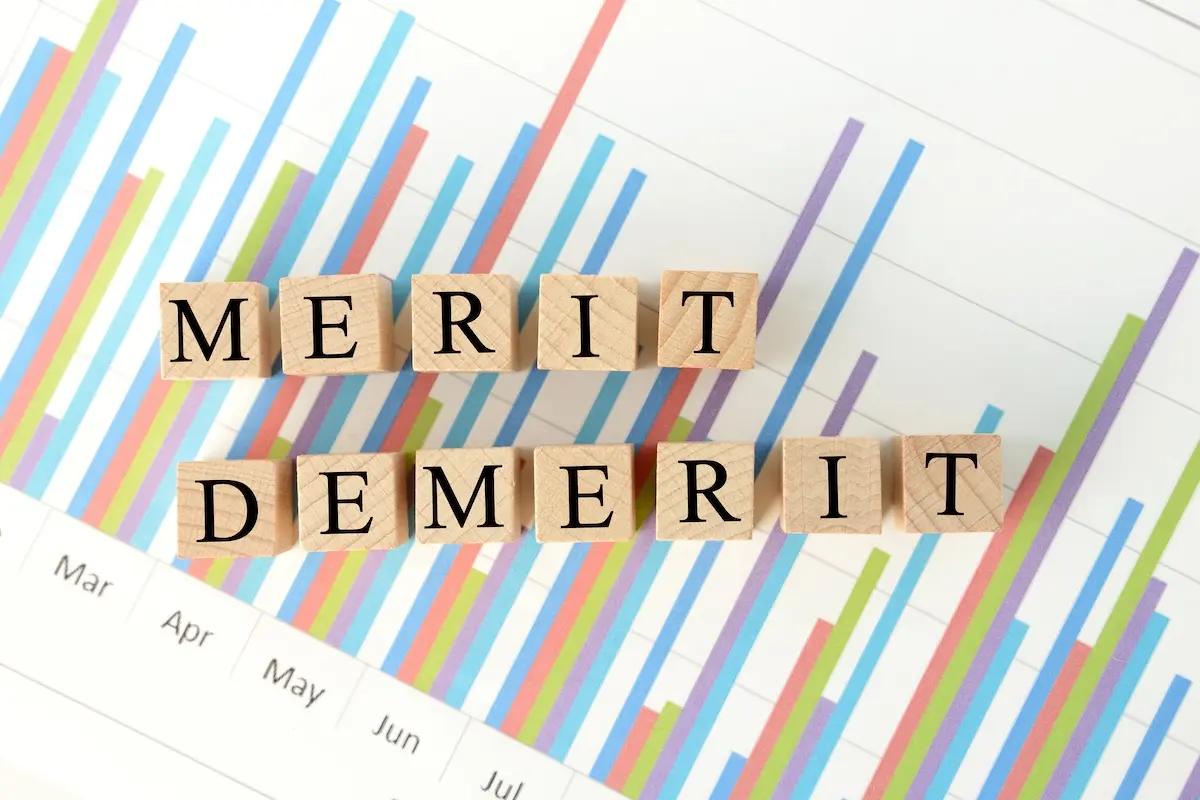
分社化は、経営の効率化をはじめ、会社に様々なメリットをもたらす手法で、近年多くの企業が採用しています。特に2000年代になると、大企業だけでなく中小企業でも分社化が活用されるようになりました。
本記事では、分社化の概要や目的、子会社化との違い、メリットやデメリットを解説します。分社化の方法や注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
▷関連記事:スピンオフの手法とは?3つのメリットや税制・事例も紹介
▷関連記事:会社分割とは?メリットから意味や種類、類型までを解説
企業価値100億円の企業の条件とは

・企業価値10億円と100億円の算出ロジックの違い
・業種ごとのEBITDA倍率の参考例
・企業価値100億円に到達するための条件
自社の成長を加速させたい方は是非ご一読ください!
分社化とは
分社化とは、企業が組織や事業の一部を分離して、独立した会社を作ることです。分社化には、特定の事業部門だけを切り離して子会社にしたり、特定の地域の部署を別の独立した会社にしたりするケースが挙げられます。
分社化によって一部の事業や部門を切り離せば、業務の効率化や経営資源の集中を進められたり、新規事業への参入にかかる手間や時間を削減できたりする場合があります。
子会社化との違い
子会社化とは、別の会社の株式の過半数を保有し、その会社の経営権を取得して支配下に置くことです。
分社化と子会社化は、本体となる会社の下に子会社を置く点では共通しています。しかし、分社化は「自社の組織や事業を切り離して子会社とする」のに対して、子会社化は「外部の会社や事業を子会社とする」点で異なります。
また、分社化の場合は親会社が子会社の株式を100%保有するケースが一般的ですが、子会社化の場合には状況に応じて様々な出資比率が見られます。
▷関連記事:M&Aによる子会社化とは?子会社とグループ会社の違いについて解説
分社化の主な目的
分社化は様々な目的で行われます。分社化の目的としてよく見られるものは以下の4つです。
・業務効率化・経営再建
・経営資源の集中・専門性の強化
・新規事業への参入
・後継者教育
以下では、分社化が一体どのような目的で行われるのか、詳しく解説します。
1 業務効率化・経営再建
分社化により、
不採算部門を切り離して影響を受けないようにすれば、業務を効率化できます。分社化は経営再建を進める企業で見られる手法の1つです。
また、業績が好調な分野を分社化によって分離すると、不採算部門が抱える負債など赤字部門のリスクを気にする必要がなくなり、収益性の高い事業に集中できて業務の効率化や経営再建を進めることができます。
2 経営資源の集中・専門性の強化
好調な分野に経営資源を集中させ、事業の成長や収益の拡大を狙って、分社化が行われることがあります。上述の経営再建のケースとは異なり、会社としてより成長するために分社化が行われるケースです。
ある事業分野で業績が悪化しても企業全体では収益を確保できるよう、企業経営においては複数の事業を展開して多角的に事業を展開するケースがありますが、逆に、選択と集中によって経営資源を特定の分野に集中させるケースもあります。このような場合に、長期的な成長や収益性の向上を目的として分社化が行われることがあります。
3 新規事業への参入
分社化は、新たな事業分野へ参入するときに使われる手法の1つです。分社化によって事業規模を小さくし、意思決定のスピードを上げれば、競合他社との競争において迅速に対応できるようになります。
新規事業へ参入するための部門や部署を新たに立ち上げて、分社化せずに既存の企業内の1つの部門・部署として対応する場合は、社内での手続きが煩雑になったり、長い歴史の中で培われた企業文化が、意思決定の足かせになったりするケースも少なくありません。
新たな事業分野に臨むにあたり、既存の企業文化に捕らわれず迅速に意思決定を行って対応するために、分社化が有効な手段の1つとなり得ます。
4 後継者教育
一部の事業を分社化して後継者候補に運営を任せれば、後継者候補は実践的な経験を積みながら経営者に必要なスキルを身に付けることができます。
最初から会社の経営を任せるのは不安な場合でも、分社化によって一部の事業について経営責任者を置けるようにすれば、親会社では従来どおり経営者が指揮を取りつつ、後継者教育も同時に進めることが可能です。
分社化による6つのメリット
分社化の主なメリットは以下のとおりです。
1 経営効率を高められる
2 意思決定を迅速に行える
3 節税効果が期待できる
4 倒産のリスクマネジメントになる
5 事業承継問題の解決につながる
6 資金調達がしやすくなる
各メリットの詳細を解説します。
1 経営効率を高められる
分社化では、経営効率を高められる点がメリットです。例えば、成長部門を子会社として独立させれば、子会社が独自に資金調達や技術協力を得ることができ、さらなる成長を見込めます。
また、グループ内にある複数の会社で取り扱う事業が重複している場合、分社化して1つの会社に事業を集約することで、グループ内の無駄を省けます。
2 意思決定を迅速に行える
刻々と変化する近年のビジネス環境において、重要な判断に対してのスピード感は重要です。しかし、企業の規模が大きくなるほど関連部門や役職が増えるため、意思決定構造は複雑化するケースが多くなります。
そこで、分社化によって意思決定構造をシンプルにすれば、その分経営における重要な判断もスピード感を持って行いやすくなります。
3 節税効果が期待できる
法人税の税率は、原則として23.2%です※1。ただし、資本金が1億円以下の中小法人の場合、課税所得額が800万円以下だと軽減税率が適用されます。そのため、分社化して事業の一部を中小法人とすると、場合によって節税効果が期待できます。
| 区分 | 税率(開始事業年度2022.4.1以降) | ||
| 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 下記以外の法人 | 15% |
| 適用除外事業者 | 19% | ||
| 年800万円超の部分 | 23.2% | ||
| 上記以外の普通法人 | 23.2% | ||
※1 参照元:国税庁 「No.5759 法人税の税率」
また、消費税は2年前の事業年度を基準期間とするため、分社化して新しく会社を設立すると2年間は消費税の納付が免除されます。
特定新規設立法人など納税義務免除の特例に該当する場合もありますが、消費税が免除される可能性がある点は分社化のメリットです。
4 倒産のリスクマネジメントになる
会社の中に業績の悪い部門があると、その部門の赤字により財務状況が悪化し、倒産するケースがあります。分社化により業績の悪い部門を切り離せば、倒産することになっても影響はその会社のみとなり、倒産リスクの軽減が可能です。
5 事業承継問題の解決につながる
事業承継で複数の後継者がいる場合、だれに事業を承継するかは難しい問題です。分社化で会社を個々に独立させると、複数の後継者にそれぞれの会社を承継することができ、事業承継問題の解消につながる場合があります。
6 資金調達がしやすくなる
分社化によって不採算部門を切り離せば、赤字部門の影響を受けなくなることで財務状況が改善し、資金調達しやすくなります。分社化して収益性の高い事業分野だけを残し、会社の財務諸表から不採算事業を切り離すと、金融機関から融資を受ける際の審査に通りやすくなる可能性があります。
分社化による4つのデメリット
分社化にはメリットがある反面、いくつかのデメリットもあります。主なデメリットは以下のとおりです。
1 分社化の手続きが必要となる
2 会社維持のコストが増える
3 株主の同意が必要となる
4 ブランド価値が分散・低下する
メリットだけでなく、デメリットを把握しておくことも分社化を成功させるポイントです。
1 分社化の手続きが必要となる
分社化して新たに会社を設立するためには、当然ながら手続きが必要となり、時間や手間がかかります。財務、税務、法務の専門的な知識が求められる場面も多く、とりわけ税務処理は、複雑な手続きが伴うケースもあるため、経験を積んだ専門家の力を借りる必要があります。
2 会社維持のコストが増える
会社の数が増えれば、それだけ維持にかかるコストは増えます。会社ごとに経理作業を行わなければならず、管理の時間的なコストや費用がかさんでしまう可能性があります。
また、分社化に際して、財務や税務、法務の専門知識を持つ人材を新たに雇い入れたり、顧問につけたりする必要もあるでしょう。社屋を新たに持つ場合は、賃料の支払いや設備の導入、維持管理費用も必要になります。
3 株主の同意が必要となる
株式会社を分社化する場合、株主総会の特別決議(3分の2以上の同意)が必要です。株主の同意を得るためには、分社化の合理的な理由やメリットを理解してもらう必要がある他、株主総会を開催する手間や労力もかかります。
4 ブランド価値が分散・低下する
企業の歴史の中で築き上げてきたブランド価値や消費者からのイメージが、分社化によって複数の企業に分散してしまい、ブランド価値の分散・低下につながる場合があります。
ブランドの一貫性が損なわれると、認知度や収益性に影響が生じる可能性があります。そのため、分社化によって会社が分かれても、企業間で連携を取ってブランド管理を行うなど、企業ブランドの一貫性を維持することが重要です。
分社化の方法

分社化には、主に以下の3つの方法が挙げられます。
1 単独型新設分社型分割
2 共同新設分社型分割
3 分社型吸収分割
各方法の特徴や事例を紹介します。状況に応じて、どの手法で目的を達成できるか検討しましょう。
1 単独型新設分社型分割
単独型新設分社型分割とは、会社(分割会社)の一部の組織や事業を切り離し、新しく設立した会社(新設会社)へ移行する方法です。分割会社は新設会社に組織や事業を承継し、代わりに新設会社から株式の割当を受けるため、新設会社は分割会社の100%子会社となります。
例えば、2023年9月14日に、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォームを運営する株式会社ツクルバが、自社の不動産企画デザイン事業を分社化する際に単独型新設分社型分割を採用しています。
2 共同新設分社型分割
共同新設分社型分割は、複数の既存会社(分割会社)がそれぞれの事業や組織の一部を切り離し、これらを合わせて独立した会社(新設会社)を設立する方法です。
この手法は、同じグループ内で同じ事業を行う複数部門を統合して経営効率を高めたい場合や、異なる会社で同様の事業を分割し、競争力を高めたい場合などに有効です。
過去には、古河電気工業とNTTエレクトロニクスが共同新設分社型分割を採用し、両社の製造事業の一部を統合して新しい会社を設立しました。この新設は、今後増加が見込まれる光部品の供給体制を強化することが狙いです。
3 分社型吸収分割
分社型吸収分割とは、会社(分割会社)が一部の組織や事業を切り離し、別の会社(承継会社)に移行する方法です。分割会社は事業を引き渡す対価として、承継会社の株式などが割り当てられます。
例えば、ソフトバンクが自社のアニメ専門コンテンツ配信サービスである「アニメ放題」を切り離し、U-NEXTに分割した事例は分社型吸収分割の一例です。ソフトバンクとU-NEXTの分社型吸収分割では、株式ではなく2億5,000万円の金銭がソフトバンクへ交付されています。
分社化する際に注意すべきポイント
分社化する際に注意すべきポイントは以下のとおりです。
・目的や期待する効果に合わせて分社化の方法を選ぶ
・分社化する時期を見極める
・専門家の意見を取り入れる
各ポイントの詳細を解説します。
目的や期待する効果に合わせて分社化の方法を選ぶ
先述のように、分社化は成長部門や不採算部門の切り離し、新規事業への参入、税金対策など様々な目的で実施されます。また、分社化の方法には、単独型新設分社型分割や共同新設分社型分割などがあり、一様ではありません。
そのため、分社化する目的や期待する効果を具体的に検討し、目的や効果に合った方法を選択する必要があります。
分社化する時期を見極める
分社化にはメリットがある一方、適切なタイミングで実施しなければ期待する効果を得られないケースも想定されます。自社の経営状況だけでなく、市場や税制など外部の環境も踏まえた見極めが大切です。
また、分社化の手続きには一定の期間が必要になるため、いつまでに実施するのか決めたうえで、そこから逆算して準備を進める必要があります。
専門家の意見を取り入れる
分社化は、方法の選択や手続き、実施時期など検討課題も多く、専門的な知識が求められます。失敗すると大きな損失を出す可能性もあるため、慎重に進めなければいけません。
自社のリソースだけで対応できない場合には、外部の専門家の意見を取り入れて多角的に検討する方法も有効です。専門知識や第三者の客観的視点を参考に意思決定を下すことが、成功への近道となるでしょう。
まとめ
分社化は経営効率を高めたり、節税効果が期待できたりと、様々なメリットのある手法です。適切なタイミングを見極め、目的や期待する効果に合わせた方法を選択すれば、自社の成長に大きく貢献します。
一方、分社化には財務や税務、法務などの専門知識が求められる場面もあります。メリットとデメリットを把握し、状況によっては専門家のアドバイスも活用しましょう。
fundbookには、財務・税務・法務など各分野の高い専門性を持つアドバイザーや士業専門家が在籍しているので、不明な点があるときはご相談ください。
