
サイトM&Aとは、個人や企業で運営しているWebサイトを売買することを指します。
サイトM&Aで売買されるWebサイトは、収益やアクセス数などが一定の基準を満たしているため、事業の拡大などを目的としてM&Aを検討している方もいるのではないでしょうか。
しかし、何も知らずにM&Aを行うと「想定していた成果が上げられず、費用だけかかってしまった」という事態を招いてしまうこともあり得ます。
本記事では、サイトM&Aとは何かを解説しています。また、サイトM&Aを行うメリット・デメリットや相場、流れ、失敗しないための注意点も紹介しています。サイトM&Aを検討している方は、ぜひ参考にしてください。
企業価値100億円の企業の条件とは

・企業価値10億円と100億円の算出ロジックの違い
・業種ごとのEBITDA倍率の参考例
・企業価値100億円に到達するための条件
自社の成長を加速させたい方は是非ご一読ください!

安田 亮
https://www.yasuda-cpa-office.com/
目次
サイトM&Aとは?
「サイトM&A」とは、文字どおりウェブサイトのM&A(売却・買収)を指します。
一般の企業間で行われるM&Aと同様、ウェブサイトや、サイトを通じて展開する事業を、他社に譲渡したり他社から譲り受けたりすることです。また、サイトM&Aは「サイト売買」とも呼ばれます。
自ら構築して育てた愛着のあるサイトを手放すことに抵抗がある場合や、成長途上であるサイトの将来性を手放すのが惜しいと感じる場合もあるかもしれません。
しかし、事業があまりうまくいかず、アクセス数が伸び悩んで想定よりも収益や効果が得られなかったり、ビジネスとしては成り立っているものの、事業を整理したいと考えていたりする場合もあるでしょう。そのようなタイミングで、サイトM&Aを検討する譲渡企業もあります。
また、多くのユーザーがアクセスする将来性が見込める優良サイトであれば、より有利な条件で譲渡することが可能です。譲り受けた企業側でサイトの魅力をさらに発展させれば、多くの顧客を獲得できます。
サイトM&Aの売買手法

サイトM&Aは、主にWebサイトの運営に関わる特定の事業を対象としたM&Aを指します。
Webサイト運営事業を行う企業の多くは、複数のWebサイトを運営しながら他の事業も行っていることが一般的です。そのため、サイトM&Aの売買手法では「事業譲渡」または「吸収分割」の2つが用いられるケースが多いです。
ただし、譲渡企業の事業が、譲渡するWebサイト運営のみの場合は、株式譲渡が用いられ企業ごと買収するケースもあります。
▷サイトM&Aの代表的な手法:事業譲渡
「事業譲渡」は、サイトM&Aの売買手法で最も一般的な手法です。事業譲渡とは、一定の事業目的のために組織化された有機的一体として機能する有形、無形の財産を一括して譲渡することと定義されています。
そのため、事業譲渡では設備などの有形財産から知的財産などの無形財産まで、多くの権利義務が譲渡対象になります。
サイトM&Aでは、主に以下のものが譲渡対象です。
| 権利義務 | 例 |
|---|---|
| ドメイン・サーバー関連 | ・ドメイン使用の権利ドメイン維持 ・更新に関連したサーバー会社などとの契約 |
| プログラム・コンテンツ関連 | ・サイトを構成する各種権利(プログラム、コンテンツなどの使用権や財産権) ・アカウントやパスワードなど |
| 会員やユーザー関連 | ・顧客情報や契約関連 |
| 取引・契約関連 | ・クライアントの情報 ・クライアントとの契約 |
| 人材関連 | ・運営スタッフの雇用契約 |
| その他 | ・ノウハウや技術など |
事業譲渡では、会社間の契約としては有形・無形の財産が一括して譲渡されることになりますが、あくまでも上記に挙げているような事例の権利義務は個別承継の手続きをとる必要があります。
例として、顧客情報などの譲渡は、事業譲渡の場合に個人情報が承継される旨が明記されていなければなりません。さらに、譲渡後は当初の利用目的に従って利用しなければならないため、専門家のアドバイスを受けて、慎重に行う必要があるでしょう。
また、債権や債務、雇用契約など、譲渡側と譲受側以外の第三者に影響する権利義務の承継を行う際は、第三者の同意も必要になる点を把握しておきましょう。
サイトM&Aによる売却相場

サイトの売却価格は、おおむね「月間売上×18〜24ヶ月分」といわれていますが、サイト規模や状況によって、売却金額が相場より高くなることもあれば、低くなることもあります。
例えば、ポータルサイトは立ち上げや運営にコストがかかり需要も高いことから「月間売上の3年~5年程度」の売却価格になるケースもあります。他方、EC系のサイトは「月間売上の1年~1年半程度」が目安といわれています。
なお、Googleのガイドラインに違反したSEO対策(ブラックハットSEO)を行うサイトは、売却金額が大幅に下がる傾向があります。
【譲渡側】サイトM&Aを行うメリット
サイトM&Aによって譲渡側が得られる主なメリットは、以下のとおりです。
・中核事業を効率的に運用できる
・譲渡益による資金調達ができる
それぞれ順番に解説します。
中核事業を効率的に運用できる
ビジネスモデルや業界によって差はあるものの、ウェブサイトの運営には多大なコストや手間がかかります。
一般的に、ネット関連企業では数多くのウェブサイトを同時に運営していますが、運営維持にかかるコストやリソースの総計は決して少なくありません。さらに、それらのサイトはアクセス数やコンバージョン数、収益性、将来性などの点でかなりの差があります。
そこで、収益性が高く経営戦略上に必須なサイトだけを残し、他のサイトは売却するなどの整理を行うことで、中核事業にコストやリソースを集中させ効率よく事業を運営できるようになります。ネット事業の選択と集中を図ることによって、効率化できるのがサイトM&Aの大きなメリットです。
譲渡益による資金調達ができる
サイトを譲渡することによって、本来得られる月間収益の数年分にあたる金額を一度に獲得できます。
ウェブサイトは実体のないものではありますが、企業にとっては非常に価値のある資産です。もちろん、サイトの価値はケースバイケースですが、優良サイトになると数百万円、時には億単位で評価額がつく場合もあります。
例えば、「資金調達プロ」のM&Aはその最たる1例です。
2015年にリリースされた同サイトは、資金調達に関わる専門家情報を集めた個人運営のポータルサイトで、アフィリエイトによる収益性の高さが評価された結果、2018年に月間売上の4〜5年分に相当する6億2,000万円という金額で上場企業の株式会社セレスに事業譲渡されました。
近年では、このような例に倣って、「サイトを作り、育てて売る」ことで事業資金を得る起業家も増えています。譲渡によってまとまった額の資金を得られれば、得た資金を別事業に回したり、新規事業を起こしたりすることもできるでしょう。
【譲受側】サイトM&Aを行うメリット
サイトM&Aによって譲受側が得られる主なメリットは、以下のとおりです。
・サイト開設にかかる時間やコストを削減できる
・サイト運営のリスクを軽減できる
上記を順番に解説します。
サイト開設にかかる時間やコストを削減できる
サイトM&Aを行う譲受側のメリットは、サイト開設にかかる時間やコストを削減でき、運営に関するリスクを軽減できることです。
例えば、コスメやサプリのECサイトを運営したい場合、新たにドメインを取得し一からサイトを構築すると、ウェブページの制作、受注・発注機能の実装、スタッフの雇用など、時間とコストがかかります。
それに対して、すでに完成されたサイトを買収できれば開設にかかる時間やコストを削減し、すぐにサイト運営を始めることができます。
開設にかかる時間やコストをできるかぎり削減したい場合は、サイトM&Aを検討しましょう。
サイト運営のリスクを軽減できる
サイトを一から開設して運営する場合、アクセス数や顧客を確保できないなどのリスクがあります。
しかし、すでに一定のアクセス数や読者・顧客を確保しており、ある程度の実績を持つサイトを譲り受けることができれば、リスクを回避しながらすぐに事業を始めることができます。
サイト自体はそのままでも、運営方針や扱う商材を見直すことによってイメージどおりのサイトに変えていければ、一からサイトを立ち上げるよりもリスクを抑えて新規事業をスタートできます。
【譲渡側】サイトM&Aを行うデメリット
譲渡側にとってサイトM&Aを行うデメリットには、以下のようなものが挙げられます。
・税金がかかる
・収入が減少する
・競業禁止になる
上記を順番に解説します。
税金がかかる
サイトM&Aは、一般的なM&Aと同様に成立しても売却金額が全て手元に残るわけではなく、個人であれば所得税や住民税がかかり、法人であれば法人税や法人住民税、法人事業税などの税金が発生します。
上記の理由から、譲渡益と実際に受け取れる手取り金額は異なるため、事前にシミュレーションしておきましょう。
収入が減少する
また、サイトM&Aでは、譲渡するサイトが一定のアクセス数や安定した収益を上げていることが条件になる場合が多いです。
そのため、売却時にはまとまった資金を得られますが、譲渡後はサイトからの継続的な収入源が失われる点を理解しておきましょう。
競業禁止になる
M&Aの成約後には、譲渡企業が競合するような事業を再度行い譲受企業に不利益を与えることを避けるため、競業禁止の義務が課されます。
サイトM&Aの場合、サイトの譲渡後に類似サイトを譲渡企業が作成してしまうと譲受企業が買収したサイトの価値が減少してしまう可能性があるため、競業避止義務条項を盛り込むケースが一般的です。
競業避止義務条項がある場合には、一定期間の競業避止義務が発生するため、定められた期間が経過するまで譲受側の不利益があるサイトを作ることはできません。
▷関連記事:「M&Aにおける競業避止義務-競業に該当するケースと従業員に課す際の注意点」
【譲受側】サイトM&Aを行うデメリット
譲受側にとってサイトM&Aを行うデメリットには、以下のようなものが挙げられます。
・手を加えにくい
・リスクも引き継ぐ
上記を順番に解説します。
手を加えにくい
サイトM&Aで譲受したサイトは、すでに一定の収益やユーザー基盤が確立されているため、安易に大きな変更を加えるのはリスクが伴います。
例えば、デザインの改修やコンテンツの追加などを行う際に、既存ユーザーのニーズを無視した改変を行ってしまい使用感が変わると、アクセス数や収益の減少につながる恐れがあります。
リスクも引き継ぐ
サイトM&Aでは、譲り受けたサイトの収益だけでなく、潜在的なリスクも同時に引き継ぐ点を理解しておきましょう。
例えば、SEO対策で過度に最適化されていたり、ブラックハットSEOのようなアルゴリズムの隙を突く手法が用いられたりする場合、検索エンジンのアップデートにより突然順位が大幅に下がるリスクがあります。
また、過去の著作権問題やクレーム履歴が後から表面化するケースも考えられるため、事前に調査し、適切なリスク管理を行いましょう。
サイトM&Aでの売買の流れ

サイトM&Aを行う主な方法は、自ら調べて行うか、M&A仲介会社・マッチングサイトなどの支援サービスを活用するかの2つに分けられます。
ここでは、支援サービスを活用した際のサイトを売却するまでの流れについて、譲渡側と譲受側に分けて解説します。
▷【譲渡側】サイトを売却するまでの流れ
M&Aによって譲渡側がサイトを譲渡するまでの流れは、以下のとおりです。
1. 売却サービス・サイトへの登録
2. 売却サービス・サイトの審査
3. 仲介契約、秘密保持契約の締結
4. 気になった相手先と交渉開始
5. 各種契約を結び、M&Aを進める
6. 譲渡対価を獲得する
1:売却サービス・サイトへの登録
まずは、サイトの売却サービスを行うサイトに情報を登録します。
2:売却サービス・サイトの審査
情報の登録が済むと、次にサイト側による審査が行われます。
3:仲介契約、秘密保持契約の締結
M&A仲介会社に支援を依頼する場合は、仲介業者と仲介契約および秘密保持契約を締結します。
また、仲介会社が譲渡企業の情報を伏せつつ、譲受企業にM&Aを打診するためにサイトページのPV数、売上、SEO対策の情報などを共有する資料を作成します。
なお、マッチングサイトを利用する際には、相手先企業とも秘密保持契約の締結を行います。
4:気になった相手先と交渉開始
相手先と日程を調整し、面談やM&Aの懸念点・疑問点の解消を行います。仲介会社に支援を依頼する場合は、M&Aアドバイザーが面談の日程調整などまで支援します。
5:各種契約を結び、M&Aを進める
基本合意を締結後、譲受側からの買収監査を受けます。結果を受け企業価値が算出されたら契約内容や条件を確認のうえ最終契約を結びます。ここでM&Aが成約します。
6:譲渡対価を獲得する
M&A成約後には、譲受企業から譲渡対価として金銭などを受け取ります。また、M&A仲介会社などの支援先に成功報酬などの費用を支払います。
▷【譲受側】サイトを買収するまでの流れ
他方、M&Aによって譲受側がサイトを譲受するまでの流れは、以下のとおりです。
1. 買収サービス・サイトの登録
2. 案件の検討
3. 気になった相手先と交渉開始
4. 各種契約を結び、M&Aを進める
5. ドメインの移管を管理会社に申請する
1:買収サービス・サイトの登録
まずは、サイトのM&A仲介サービスを行う業者に情報を登録します。
2:案件の検討
交渉を申し込んだら、案件一覧より基本的な情報を得てM&Aを検討します。また、譲渡側が運営するサイトの情報を閲覧し、さらに詳しい情報を必要とする場合には、相手先への面談を要請します。
3:気になった相手先と交渉開始
相手先と日程を調整し、面談やM&Aへの懸念点・疑問点の解消を行います。M&A仲介会社に支援を依頼する場合は、M&Aアドバイザーを通して日程の調整が行われます。
4:各種契約を結び、M&Aを進める
基本合意を締結後、譲渡側の運営状況などに関して買収監査、いわゆるデューディリジェンスを行います。結果を加味した企業価値が算出されたら契約内容や条件を確認のうえ最終契約を結び、M&Aが成立します。
5:ドメインの移管を管理会社に申請する
ウェブサイトの住所であるドメインは、ドメイン管理会社によって管理されています。そのため、まず譲渡側で管理会社に移管の申請を出し、手続きをします。細かな方法は管理会社によって異なるため、M&Aが成立したらドメイン管理会社に問い合わせて対応方法を確認しましょう。
サイトM&Aで失敗しないための注意点とポイント
サイトM&Aで失敗しないためには、事前準備と細やかなフォローが重要です。
ここでは、サイトM&Aで失敗しないための注意点を紹介します。ぜひ参考にしてください。
▷売買契約前のデューディリジェンスは入念に行う
一般的なデューディリジェンスではあらゆる項目について調査が行われますが、サイトM&Aの場合のデューディリジェンスは、調査対象がWebサイトのみに限られます。
譲受側は、サイトの価値や将来性を譲渡側から提出された資料をもとに判断しなければいけないため、デューディリジェンスをより慎重に行う必要があります。
デューディリジェンスを疎かにしてしまうと、M&Aが失敗する可能性が高くなるため、徹底的に確認するようにしましょう。
デューディリジェンスで確認する主な項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 確認するポイント |
|---|---|
| アクセス・収益関連の確認 | ・サイトのコンバージョン数やページビュー数といったアクセス指標や財務指標などのデータが正確かどうか など |
| SEO関連の確認 | ・ブラックハットのような手法をとっておらず、正当に評価されているか など |
| その他の確認 | ・クレームや情報漏洩など、M&A成立後に譲受側が不利益を被る可能性が無いか など |
収益関連の確認には、譲渡側が提出したデータを確認するだけではなく、アナリティクスの閲覧を許可してもらうなど、実際のデータと提出されたデータに差異がないかを厳密に調査するのがおすすめです。
また、データに残っておらず交渉で不利になるような潜在的リスクを譲渡側が隠している可能性もあります。例えば、ECサイトの場合、商品の仕入れ先とのトラブルをきちんと伝えていないなどのリスクがあります。
M&Aの成立後、円滑に運営ができるように気になる点は全て確認しておきましょう。
コンテンツの移管は権利関係に注意する
M&Aが成立すると、サイトで使用中の画像やデザインデータなどのコンテンツを取りまとめ、譲受側に引き渡します。この時に注意したいのが、著作権の所在です。
フォトグラファーに依頼して撮影した画像や、外部のライターが作成した記事、サイト内で使用するシステムなどの著作権や所有権は、必ずしもサイトの所有者にあるとは限りません。契約内容によっては、コンテンツを作成した人にある場合があります。
そのままではサイトの売却自体ができないため、特に外注したコンテンツについては権利の所在を必ず確認しておきましょう。そして、既存のコンテンツがそのまま掲載し続けられるよう、許可を得る必要があります。
また、ドメイン名については類似の名称が商標登録されている場合があります。商標権侵害の可能性がないかどうかについても確認しましょう。
サーバーの移管には選択肢がある
データを置くサーバーに関しても、そのまま引き継ぐか、あるいは別のサーバーを立てるかを選択します。移管する必要がない場合は、サーバー管理会社に名義変更の申請をします。
なお、譲受側がすでに別のウェブサイトを運営している場合、サーバー管理会社は一本化できたほうが、管理の負担が少なくなる場合が多いでしょう。一本化する際は、新たにサーバーを立てて、移管手続きを行う必要があります。
運営ノウハウの移管はきめ細やかに行う
サイトの種類によって、運営するための実務作業は大きく異なります。日常的に行う更新作業や問い合わせへの対応、週ごとや月ごとに行うメンテナンスなど、運営の実務内容は細かく多岐にわたります。
そのため、譲渡側で運用マニュアルをまとめ、譲受側に引き継げると良いでしょう。
また、譲渡後は、マニュアルに記載していないイレギュラーな事案が突発的に発生することもあるため、譲渡側はM&A実施後も一定期間サイトの運営に関わり、譲受側からの問い合わせに対応できるようにすることをおすすめします。いずれにせよ、運営のノウハウはできるだけ詳細にマニュアル化し、漏れなく引き継ぐことが重要です。
外部スタッフへの引き継ぎもしっかりと行う
サイトの運営に外部スタッフが大きく関わっている場合は、その引き継ぎも行う必要があります。定期的な記事の投稿やサイト運営そのものを外部に任せている場合などは、サイト所有者が変わることを知らせたうえで引き継ぎ、運営を継続してもらえるように交渉しましょう。
特にECサイトでは、受注・発注業務や倉庫からの発送など、多くを外部に委託しているケースが一般的です。その場合、新所有者の名義で契約し直す必要があるため、契約条件を確認し、引き継ぎを行いましょう。
手数料や税金に注意する
サイトM&Aにかかる費用は、契約に関わるものだけではありません。仲介業者などの専門家にサポートを依頼すれば手数料がかかりますし、M&A成立後には各種税金が発生します。
M&Aの手数料は、一般的に「基本料+取引額×数%」を請求する仲介業者が多く、数十万円単位の費用がかかると考えておいた方が良いでしょう。
料金体系は仲介業者によって異なるため、手数料を少しでも抑えたい場合は、インターネットや無料相談などを活用し料金の安い仲介業者を探すことをおすすめします。
また、M&Aでは費用がかかるタイミングがいくつかありますが、最も比率の高い費用が税金です。発生する税金の種類や税率はM&Aのスキームによって異なりますが、個人の場合、長期譲渡所得に該当すれば所得税および住民税がおよそ20%程度、法人の場合は法人税などがおよそ30%~40%かかります。もしサイトM&Aで手に入れたい目標金額があるのであれば、手数料や税金も計算に入れた交渉を検討してみましょう。
売れるサイトと売れないサイトの違いとは?
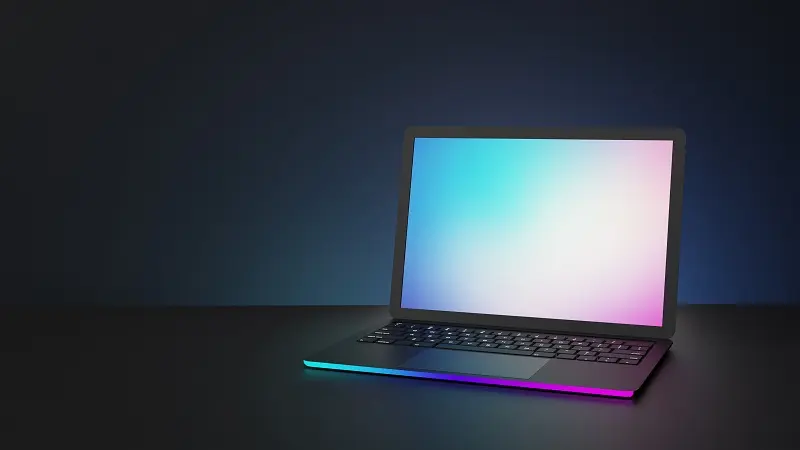
前述したように、ウェブサイトの評価額は状況やタイミングによって異なり、非常に高い金額で売却できることもあります。一方、なかなか譲り受け先候補が見つからず、見つかっても評価額が低いということもあります。
このような価格の差は、主にサイトのビジネスモデルや扱う商品・サービスの価格帯によって生まれます。そこで、売れるサイトと売れないサイトの違いを考えてみましょう。
安定した収益を実現できるビジネスモデルか
一般的にサイトM&Aで譲受側から人気があり、価格が高めになるのはアフィリエイトやアドセンスによって安定した収益を上げているサイトです。これらのモデルは「日々、手を入れなくてはならない」というものではありません。つまり、ある程度放置しておいても稼いでくれるサイトです。
一方、ECサイトは、受発注業務や顧客対応などに工数がかかるため、サイトM&Aのニーズは比較的多くありません。ただし、商材や売上次第では大きな譲渡対価を得られる可能性もあります。
需要の多い価格帯であるか
サイトM&Aでは数百万から数千万円の高値がつく場合もありますが、そうしたサイトは運営にもそれなりの時間やコストがかかるため、「サイトを譲り受けて手早く事業を始めたい」という譲受側のニーズがあったとしても、リスクが高すぎることもあります。
売れやすく買いやすいサイトは、現状の運営である程度の収益があり、運営ハードルも高くなく、失敗しても納得して損切りできるレベルのサイトです。金額的にはおおよそ50万円から100万円までが需要の多い価格帯と言われています。
SEO(=検索エンジン最適化)への対策がされているか
ビジネスサイトの運営では、検索エンジンのアルゴリズムに対応したSEO(検索エンジン最適化)対策を施すのが一般的です。
ただし、SEOの施策には複数の種類があります。アルゴリズムに従い、検索エンジンに評価されやすい優良なコンテンツなどを投入している手法を「ホワイトハット」、逆にアルゴリズムの裏をかき、不正に順位を上げようとする手法を「ブラックハット」と呼びますが、その中間にあたる「グレー」な手法を使ったサイトも数多く存在します。
ブラックハットの手法を用いたサイトは、検索エンジンに不適切と判断されると検索結果から弾かれるリスクがあるため、サイトM&Aの中でも全般的に相場が低い傾向にあります。対して、ホワイトハットの手法を用いるサイトは、相場が高く設定されています。グレーなサイトは、価格面でもブラックハットとホワイトハットの中間の価格帯となります。
グレーなサイトは、ブラックハットサイトほど強いペナルティを受ける可能性は低くなるものの、安全というわけではありません。検索エンジンはユーザーのニーズに応えることを第一に考え優良コンテンツが上位に表示されるよう定期的にアップデートを行っています。そのため、サイトビジネスの将来性を考える場合、ホワイトハットのSEO対策を施すサイトであることがとても重要です。
代表的なサイト売買のM&Aサービス
ここでは、サイト売買を取り扱うM&Aサービスの中で代表的なものをご紹介します。
ラッコM&A

| 企業名 | ラッコ株式会社 |
|---|---|
| URL | https://rakkoma.com/ |
| 本社 | 東京都渋谷区道玄坂1-19-12 道玄坂今井ビル4F |
| 特徴 | サイト売買のM&Aにおいて、成約数・掲載案件数ともに最大級のプラットフォーム。売却手数料が無料、ラッコM&A提携弁護士への無料相談などサポートが充実。 |
BATONZ

| 企業名 | 株式会社バトンズ |
|---|---|
| URL | https://batonz.jp/ |
| 本社 | 東京都中央区築地3-12-5+SHIFT TSUKIJI 5階 |
| 特徴 | 日本最大級のM&Aマッチングプラットフォームとなり、サイト売買の案件も多数掲載。会員数も多く抱えており、M&Aの累計成約数は2,000件以上。 |
TRANBI

| 企業名 | 株式会社トランビ |
|---|---|
| URL | https://www.tranbi.com/ |
| 本社 | 東京都港区新橋5-14-4 新倉ビル6F |
| 特徴 | BATONZと並び日本最大級のM&Aマッチングプラットフォーム。サイト売買の案件の他、多様な案件を多数掲載。 |
サイトストック

| 企業名 | 株式会社サイトストック |
| URL | https://sitestock.jp/ |
| 本社 | 東京都渋谷区神南1-15-3 神南プラザビル5F |
| 特徴 | 業界トップクラスの取引実績。1,000以上の非公開案件も多数保有。 |
▷サイト売買Z
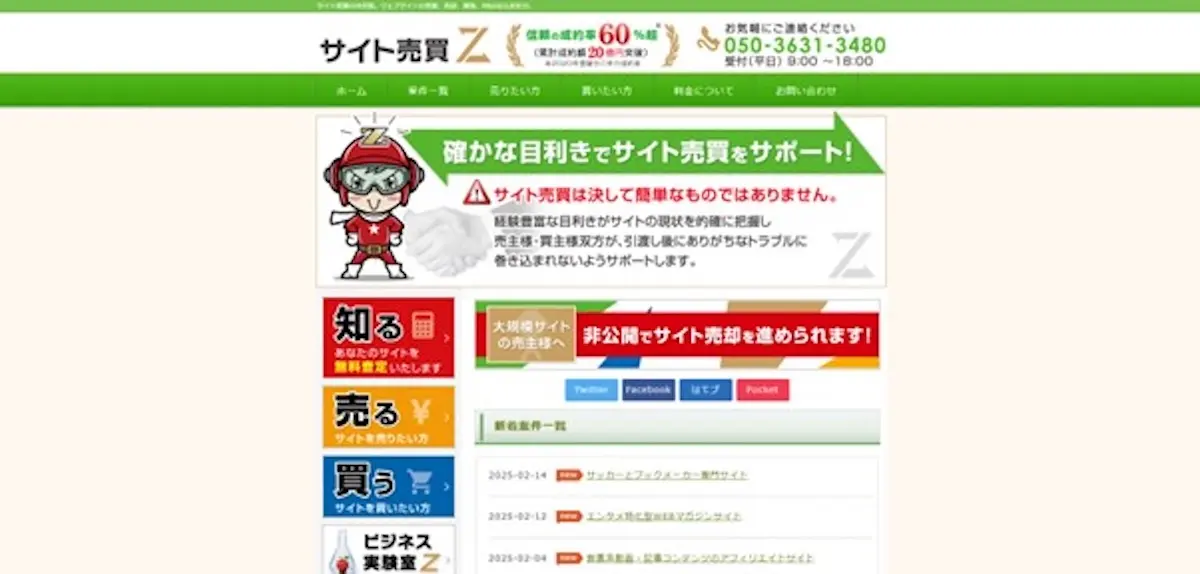
| 企業名 | 株式会社サイトM&Aパートナーズ |
| URL | https://www.site-z.com/ |
| 本社 | 福岡県福岡市西区横浜1-26-26 |
| 特徴 | サイト運営、売買の経験を積んだ担当者が仲介。サポートが手厚いため初めてのサイト売買でも安心。 |
▷サイトマ

| 企業名 | エベレディア株式会社 |
| URL | https://saitoma.com/ |
| 本社 | 東京都港区六本木4丁目3番11号 六本木ユニハウス223 |
| 特徴 | サイト売却に関わる様々な作業をワンストップで代行する業界唯一のサービス。成約率は9年連続90%を超え、案件の半数が1ヶ月以内に成約。 |
サイト運営企業のM&A事例
最後に、サイトM&Aに関連する売買事例を3つ解説します。サイトM&Aに関する公表事例は限られるため、ここではサイトM&Aに関する事例として、サイトを運営する企業のM&A事例を紹介します。
また、上段で紹介した「サイトM&Aをメインに扱う業界特化型の各M&Aプラットフォーム」からは、企業事例ではなく実際行われている様々なサイトの売買事例を確認できます。
1. アマゾンのオンライン薬局サービスを提供する企業のM&A
2018年6月、アメリカのアマゾン・ドット・コムはオンライン薬局の新興企業であるピルパックを約10億ドル(当時のレートで約1,100億円)で買収することに合意しました。
ピルパックは全米50州で通信販売薬局のライセンスを保有し、複数の薬を服用時間ごとに仕分けして自宅に配送するサービスを提供しているWebサイトを運営している企業です。
今回のM&Aにより、アマゾンはヘルスケア分野に参入し、全米規模の医薬品ネットワークを手に入れることになりました。
2. LINEヤフー株式会社(旧ヤフー株式会社)によるレシピ動画サイトを運営する企業のM&A
2018年7月、LINEヤフー株式会社(旧ヤフー株式会社)は、レシピ動画サービス「kurashiru(クラシル)」を運営するdelyを約93億円で追加出資し、子会社化すると発表しました。
クラシルは2016年に開始され、1万8,000本のレシピ動画を掲載し、アプリダウンロード数は1200万件、SNSフォロワーは290万人と国内最大級の規模を誇ります。
しかし、delyの2017年10月期の売上高は約2億8,900万円で、営業赤字は30億
6,700万円となっていました。
LINEヤフー株式会社(旧ヤフー株式会社)は出資比率を15.9%から45.6%へ引き上げ、取締役の過半数を派遣するとともに、自社サイトでレシピ動画を配信し、クラシル利用者の拡大や食材購入サービスを検討し、コンテンツ力と収益力の強化につなげるとしています。
3. 株式会社エイチームによる技術情報共有サイトを運営する企業のM&A
2017年12月、株式会社エイチームは、プログラマ向け技術情報共有サイト「Qiita」を運営するIncrements株式会社の全株式を取得し、同社をグループ会社化することを発表しました。
Incrementsは「エンジニアを最高に幸せにする」をミッションに掲げ、技術情報共有サイトの「Qiita」やチーム内情報共有ツール「Qiita:Team」を展開している企業です。
他方、エイチームは、インターネットやスマートデバイス向けのゲームコンテンツや情報サイト、ECサイトの企画や開発、運営を行う総合IT企業です。
今回の買収によりエイチームの事業開発ノウハウを活用し、サービスの改善や拡大を図ります。
信頼できるコンサルタントはサイトM&Aを行う際にも不可欠

近年、サイトM&Aは盛んに行われています。手持ちのサイトを譲渡することで事業資金を手に入れたり、イメージに近いサイトを譲り受けることですぐに新規事業をスタートさせたりと、譲渡側・譲受側の双方に利益をもたらすことができます。
サイトM&Aでは、時には数百万円から数千万円という高値がつく場合もありますが、一般的なM&Aと比べてまだまだ市場が小さく、情報も行き届いていません。そのため、どのように取引を進めていけば良いのかわからない方も多いと思います。
実際、過去にはサイトM&Aで競業避止義務条項がなかったことによるトラブル事例もあるため、実行する際には注意点を把握しておく必要があります。
また、M&Aを行う際は高い専門知識や経験が必要となり、M&Aの知識や交渉テクニックがないと、本来の価値に比べて低価格になったり、希望とは沿わない形で取引を終えることになったりしてしまいます。
納得できるサイトM&Aを行うためには、専門のM&Aアドバイザーによるサポートを受けることをおすすめします。
サイトの売買も一般のM&A同様、譲受側と譲渡側のM&Aであることに変わりはありません。公正な視点と専門知識、豊富な経験を持ち、何より信頼できるM&Aアドバイザーがいれば、譲渡側と譲受側、双方のメリットとなるM&Aが成立しやすくなることでしょう。
・fundbookのサービスはこちら(自社の譲渡を希望の方向け)
・fundbookのサービスはこちら(他社の譲受を希望の方向け)
