
M&Aでは、企業価値を的確に評価することが必要です。EBITDAは、企業の収益力を測るうえで、会計基準の違いによる影響を受けにくいという特徴を持ちます。
そのため、日本企業だけでなく、グローバルな企業比較においても、共通の尺度として活用されています。本記事では、EBITDAの意味と計算方法やМ&Aとの関連性について詳しく解説します。
上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド
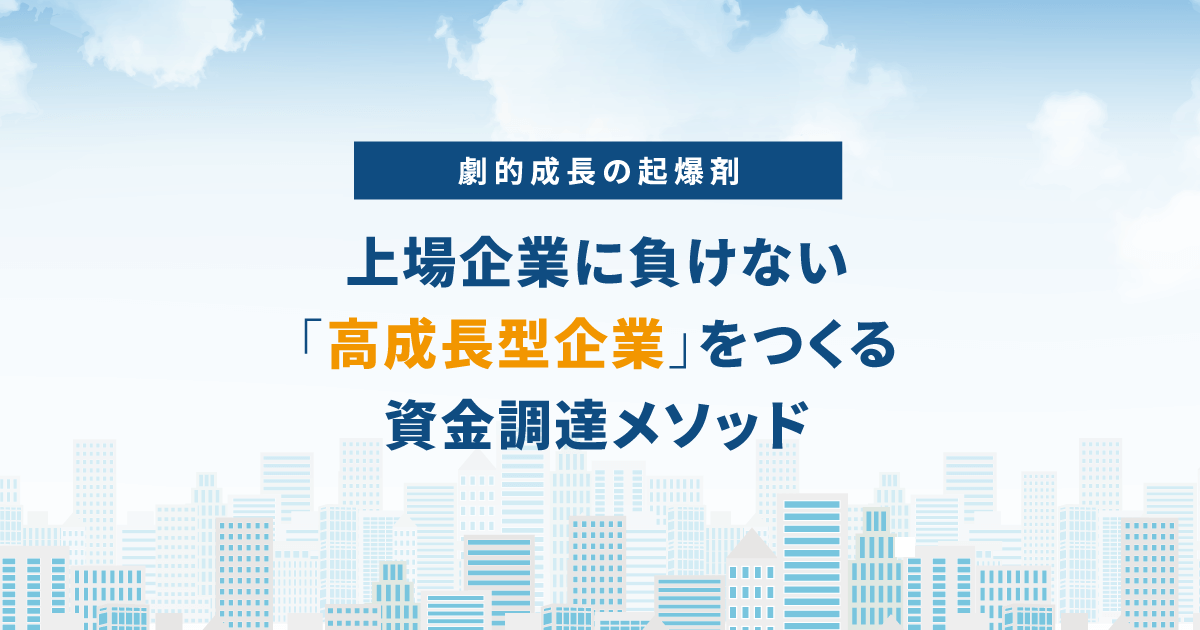
本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。
・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?
・まず必要な資金力を増強させる仕組み
・成長企業のM&A事例4選
M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。
EBITDAとは? | 意味・読み方
EBITDAとは、「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization」の頭文字をとった略語で、「利払前税引前償却前利益」のことです。支払利息や税金、減価償却費を控除する前の実質利益の一種で、一般的には「イービットディーエー」や「イービッター」などと呼ばれます。
E(Earnings)=収益、利益
B(Before)=前
I(Interest)=利息、受取
T(Taxes)=税金
D(Depreciation)=有形固定資産(建物や設備など)の減価償却費
A(Amortization)=無形固定資産(ソフトウェアや「のれん」など)の償却費
M&Aでは、企業の価値を測るために様々な指標が用いられますが、EBITDAもその1つです。
EBITDAは、企業価値評価(バリュエーション)の際、手法の1つである「マーケットアプローチ」で活用されます。
▷関連記事:【企業価値評価】マーケットアプローチとは?よく使われる計算方法やシミュレーション方法
EBITDAを使う目的
「EBITDA」はキャッシュの出入りのみに注目し、設備投資の額やタイミングに左右されずに「会社が利益を上げているか」を正確に測ることができる指標です。
一般的に、企業の価値や業績を表す指標としては営業利益が用いられます。しかし、営業利益は企業が保有する有形・無形の固定資産に対する減価償却費を控除したものであり、必ずしも企業が稼いだキャッシュの額と一致しません。
営業利益を評価指標とすると、売上が変わらなくても、設備投資が償却されて減価償却費が少なくなることで営業利益が上昇し、利益が改善しているように見えることがあります。
特に、通信業や鉄道業などの社会基盤を支える企業や製造業では、設備投資にかかる減価償却費によって営業利益が相殺されてしまうこともあります。これでは、企業の収益状況を正確に測ることができません。
そのため、減価償却費に左右されず、「キャッシュの出入り」のみに着目したEBITDAが、企業評価の重要な指標として用いられるのです。
EBITDAの計算方法
EBITDAの計算方法は、企業の会計処理や分析目的によって多岐にわたり、企業の特性や分析の焦点に合わせて柔軟に選択できる点が特徴です。
EBITDAを計算する際、よく使われる計算式は以下のとおりです。
・EBITDA=営業利益+減価償却費
・EBITDA=経常利益+支払利息+減価償却費
・EBITDA=税引前当期純利益+特別損益+支払利息+減価償却費
・EBITDA=当期純利益+法人税等+ 特別損益+支払利息+減価償却費
EBITDAの算出において最も一般的な計算式は、「営業利益+減価償却費」です。簡単に言えば、「支払利息や税金、減価償却費の控除前の利益」のことです。
営業利益とは、企業が本業で得た利益であり、支払利息や税金が差し引かれる前の段階での利益を意味します。減価償却費は、建物や機械設備などの固定資産の価値が時間の経過とともに減少していくことを考慮し、その減価分を費用として計上するものです。
EBITDAとEBITの違い
EBITDAとよく似た指標に「EBIT」があります。
| 指標 | 計算式 | 意味 | 目的 |
| EBITDA | 営業利益+減価償却費 | 支払利息、税金、減価償却費を控除する前の利益 | 国籍や規模が異なる企業価値を比較する際に使われる指標 |
| EBIT | 経常利益+利息(支払利息-受取利息) | 支払利息と税金を控除する前の利益 | 本業から得た利益に着目した指標 |
EBIT(イービット)は「Earnings Before Interest and Taxes」の略語で、利払前・税引前利益を意味します。
EBITの計算方法は1つではなく、企業がどのような視点で分析したいかによって、計算方法が異なります。一般的には、以下の計算式が使われます。
・EBIT=経常利益+利息(支払利息-受取利息)
企業が借入金によって資金調達を行うと、その対価として支払利息が発生します。EBITは、借入金による資金調達コストの影響を除外することで、企業の本業から得られる純粋な収益力を測ることを目的とした指標です。受取利息は、企業の本業から得られる利益ではないため、差し引きます。
EBITDAは減価償却費も加味しますが、EBITは減価償却費を含みません。そのため、EBITは、企業のキャッシュフローよりも収益力をより直接的に反映する指標と言えます。
EBITDAが国際的な企業間の比較に広く用いられる一方で、EBITは企業の本業から生み出される純粋な収益力に焦点を当てています。
EBITDAとフリーキャッシュフローの違い

フリーキャッシュフローとは、企業が自由に使えるキャッシュの量を示す指標で、計算方法はさまざまですが、一般的には設備投資や運転資金の増減を考慮して算出します。
フリーキャッシュフロー=営業利益 + 減価償却費 – 設備投資の増加額 ± 運転資金の増減額
一方、EBITDAは、運転資金や設備投資に投入された現金など、企業存続のために必要なコストが反映されていないため、フリーキャッシュフローとは異なります。EBITDAは、あくまで営業活動から得られる利益を測る指標であり、フリーキャッシュフローのように投資や資金繰りを考慮したものではありません。
フリーキャッシュフローは「企業全体で最終的に残るキャッシュ」を示し、EBITDAは「本業から生み出された利益」を示すと覚えておきましょう。
EBITDAを指標に使うメリット
EBITとEBITDAは似たような指標のように思われますが、M&A関連ではEBITDAのほうがよく使われており、それには明確な理由があります。M&Aにおいて、EBITDAを指標に使う主なメリットは、以下の4つです。
・中長期的な視点での企業価値評価が可能
・借入金や税の影響を排除して比較できる
・投資の償却方法の違いを排除して比較できる
・国や規模の異なる企業の収益性を比較できる
中長期的な視点での企業価値評価が可能
製造業などでは大規模な設備投資が欠かせません。そのため、減価償却費を差し引いた営業利益だけに着目すると、「正確な利益」が見えにくくなります。
また、継続した投資がない場合、当初の投資に対する減価償却費は年々減少していくため、相対的に営業利益が増えていき、営業利益だけに着目すれば業績が伸びているように見えてしまいます。
EBITDAを指標とすれば、減価償却費の影響を除外し、企業の本業から生み出されるキャッシュフローをより正確に反映できるため、中長期的な視点での企業価値評価が可能です。
国や規模の異なる企業の収益性を比較できる
世界各国で採用されている会計基準や税制は多種多様であり、減価償却の方法や税率も異なります。そのため、当期純利益は、企業の経営環境や会計処理の違いによって大きく左右され、国際的な比較・分析には不向きです。
EBITDAは、企業の純粋な収益力を測るための指標です。 借入金や税金などといった外部要因や減価償却方法などの会計処理上の違いを排除することで、企業の実力をより客観的に比較できます。
EBITDAなら、国や企業ごとの会計上の差異を中和できるため、国や規模の異なる企業の収益力をより客観的に比較することが可能です。
また、EBITDAマージンは、企業の売上高に占めるEBITDAの割合を示す指標です。企業が生み出すキャッシュフローの規模を、売上高との関係において相対的に評価できます。EBITDAマージンを用いれば、規模が異なる企業であっても、収益性を客観的に比較することが可能です。
EBITDAマージン=EBITDA÷売上高
EBITDAを活用する際の注意点
EBITDAを活用する際に注意すべき点を解説します。
・過剰な設備投資による損失はマイナス要素として認識できない
・企業に残るキャッシュは把握できない
・本来より少ない収益力に見えることがある
過剰な設備投資による損失はマイナス要素として認識できない
EBITDAの算出式「営業利益+減価償却費」における「減価償却費」は、工場新設などの設備投資を数年間に分割して費用計上した「将来生み出される未来の利益」と解釈することができます。
しかし、利益を生み出すために行った設備投資が結果的に過剰なものとなり、損失となってしまう場合があります。EBITDAではこれを認識することができません。
過剰な設備投資を行うと、基本的には売上に対する減価償却費の比率が高くなります。投資が一定期間後に必ずしも価値を生み出すとは限らない点は、EBITDAを活用するときに注意が必要です。
企業に残るキャッシュは把握できない
EBITDAは、企業の本業の収益性を簡便に評価するための指標ですが、支払利息や税金、減価償却費を差し引く前の数値です。そのため、EBITDAの金額がそのままキャッシュとして残るわけではありません。
例えば、EBITDAが高くても、借入金の返済や設備投資に多額の資金が必要な場合は、企業の財務状況は必ずしも安定しているとは言えません。企業に残るキャッシュを把握したい場合は、 キャッシュフロー計算書の確認が必要です。
本来より少ない収益力に見えることがある
EBITDAを正確に把握するためには、正常利益に基づいた計算が重要です。 正常利益とは、企業が通常の事業活動から得られる、持続可能な利益を意味します。
例えば、多額の特別費用や一時的な収入など、本業の収益力を正確に反映していない要素が含まれていると、EBITDAが歪められてしまうことがあります。このような要因を除外することで、企業の正確な収益力を把握できるのです。
具体的には、以下のケースが考えられます。
過剰な役員報酬や福利厚生費:役員報酬や保険料が一般的な水準よりも高い場合、企業の収益力が低く見積られてしまう可能性があります。逆に、これらの費用が平均的な水準よりも低い場合、稼ぐ力が少ないのにも関わらず、利益が出ているように見えます。役員の報酬や保険料の影響を取り除いて比較する必要があります。
節税目的の支出:税金を減らすための支出は、本業の収益力とは直接の関係がないため、除外する必要があります。
粉飾会計:意図的に利益を過大に表示したり、損失を隠したりする行為は、EBITDAの正確性を損なう要因となります。
EBITDAを分析する際は、企業の特別な事情や会計処理に注意を払うことが重要です。 正常利益に基づいたEBITDAを算出することで、客観的な企業評価が可能になります。
EBITDAの改善方法
EBITDAを改善するための具体的な方法として、以下の3点が挙げられます。
・売上高・営業利益の増加
・コスト削減
・負債の減少
売上高・営業利益の増加
新規顧客の開拓や既存顧客への販売促進、新製品やサービスの開発など、売上を拡大する取り組みが重要です。商品やサービスの価格の見直しも、収益向上につながります。
コスト削減
原材料費や人件費、水道光熱費などのコスト削減は、直接的にEBITDAを改善します。
業務の効率化や無駄な経費の削減も効果的です。コスト削減により、利益率が向上し、企業の収益基盤が強化されます。
負債の減少
借入金の返済や、有利子負債の削減は、企業の財務体質を改善し、EBITDAを改善する効果があります。負債が減少すると、金利負担が軽減され、利益が増加します。
M&AとEBITDAの関連性
M&Aで企業の合併や買収を行う場合、当期純利益だけでは判断が困難です。EBITDAは、企業の収益性を測るための有用な指標として使用できます。
EBITDAは、企業規模や国境を越えた比較を可能にする、普遍的な収益性指標です。特に、グローバル化が進む現代において、その重要性は増しています。
EV/EBITDA倍率とは?
EV/EBITDA倍率とは、EBITDAを利用した株価算定方法で、企業価値がEBITDAの何倍かを表す指標です。
上場企業のM&Aでは、ファイナンス理論に基づいた厳密な評価手法を用いて、最適な買収価格を算出します。
非上場企業のM&Aの場合、似た業種の上場企業のEV/EBITDA倍率と比較すると、株価の目安がわかります。同業の上場企業の公開情報から簡単に計算できるため、コストを抑えつつ株価の目安を判断できる点がメリットです。
非上場企業のM&Aにおいては、EV/EBITDA倍率を用いた企業評価は有効な手段の1つと言えます。
EV/EBITDA倍率の計算方法
EV/EBITDA倍率の計算式は、以下のとおりです。
EV/EBITDA倍率=EV÷EBITDA
EVは、その企業の時価総額にネットデット(純有利子負債)を足した値であり、企業価値と呼ばれます。EV/EBITDA倍率が小さければ小さいほど、短期間で買収にかかるコストを回収できるため、その企業が割安だと評価されます。
EV/EBITDA倍率の活用例
M&Aでは、EV/EBITDA倍率を用いた企業価値評価が広く行われています。
以下で、類似会社比較法(マルチプル法)による株式価値の計算方法を解説します。類似の上場企業のEBITDA倍率を参考に、対象企業の株式価値を算出する方法で、客観的な評価が可能です。
1. M&Aの対象企業と類似した事業を営む、複数の上場企業のEVとEBITDAを用いて、それぞれのEBITDA倍率を算出し、その平均値を求める
2. M&A対象企業のEBITDAに類似企業平均のEBITDA倍率を乗じて対象企業のEVを計算する
3. 2.で算出された対象企業のEVに、非事業用資産を加え、有利子負債を控除して株式価値を計算する
まとめ
EBITDAとは、支払利息や税金、減価償却費を控除する前の実質利益の一種で、企業の本業による収益力を測るうえで有効な指標です。M&Aなど、企業評価の場面で広く活用されています。
ただし、EBITDAは過去の業績に基づいた指標であり、将来の成長性やリスクを完全に反映しているわけではありません。M&Aでは、EBITDAに加え、将来のキャッシュフロー予測や業界分析など、多角的な視点から企業を評価する必要があります。
専門家の知見を活用すれば、より精緻な企業評価が可能になり、譲渡企業・譲受企業の双方にとって納得できる取引を実現できるでしょう。
