
年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法
・M&Aの進め方や全体の流れ
・成約までに必要な期間
・M&Aに向けて事前に準備すべきこと
会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!
目次
SPC(特別目的会社)とは
SPCとは「Special Purpose Company」の略で「特別目的会社」を指し、特別目的会社は事業内容が特定され、その特定の事業のために設立された会社をいいます。
このうち、資産の流動化に関する法律(以下「SPC法」)によって資産の流動化を目的として設立される会社を「特定目的会社」(以下「TMK」)といいます。つまり、SPC法におけるTMKはSPCに含まれる概念です。
また、より大きな概念としては、特別目的事業体(Special Purpose Vehicleの略、以下「SPV」)があり、このうち法人格を有するものをSPCと呼んでいます。 SPVのうち法人格のあるものがSPCであり、SPCのうちSPC法により設立されたものがTMKという関係になります。
なお、TMKは特定目的「会社」と呼ばれるものの、SPC法により設立される社団法人であり、会社法上の会社ではありません(SPC法2条3項)。
・SPV(特別目的事業体):特定の資産を保有するために設立された会社や組合、信託のこと
・SPC(特別目的会社):SPVのうち法人格のあるもの
・TMK(特定目的会社):SPCのうちSPC法により設立されたもの
▷SPCとペーパーカンパニーとの違い
登記上設立されているものの事業活動の実態がない会社は、ペーパーカンパニーと呼ばれます。
TMKに代表される資産の流動化のためだけに設立されたSPCも、それ自体は事業活動の実態がないとみえるものの、資産の流動化等特定の目的で設立され、その目的を果たしている点で、ペーパーカンパニーとは実質的に異なるものといえるでしょう。
▷SPCとの親子関係と計画段階の注意
後述しますが、一般的にM&AにおいてSPCを利用するスキームにおいて譲受企業が対象会社(譲渡企業)を譲り受けるために「買収目的会社SPC(会社法上の会社であってTMKではありません)に対して出資をして設立する」というものがあります。
SPCが金融機関等から借入を行い、当該SPCが対象会社の株式を取得後、SPCと対象会社を合併させて子会社化する、という形でM&Aを完了するのです。
この場合、当該SPCと譲渡企業は100%親子関係になり、その後両者が合併し、買収会社と合併後の対象会社が親子関係になります。
しかし、SPCは特定の目的のために設立された法人をいいますから、目的の如何によってSPCの設計は様々です。必ずしも設立を計画した会社と親子関係を有するわけではありません。
また、「親子関係」といっても会計上連結されるのか、また税務上の扱いについてはそれぞれ判断の基準があるため、一概には言えません。
SPCを用いたスキームについても設計を誤ってしまうと税務上の優遇を受けられなかったり、会計上不利なものになってしまうこともあり得ます。
そのため設立する会社とSPCとの関係については、その後の計画を踏まえて専門家と十分に協議して実行する必要があります。
▷関連記事:M&Aとは?M&Aの意味・流れ・手法など基本を分かりやすく【動画付】
▷関連記事:M&Aにおける合併とは?意味や手続き、種類の違いを解説
SPC法とは

SPC法とは、「資産の流動化に関する法律」のことを言います。
これは、平成10年に施行されていた「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」(以下「旧SPC法」)を、より使い勝手を良くしようという趣旨で、対象資産を財産権一般に拡大し、名称もそれに合わせて変更し、平成12年に改正・施行されたものです。
旧SPC法は、SPCを利用した資産証券化の促進を目的とし、海外SPCの利用による国内の空洞化を防止しようとするものでした。
それをより使いやすくしたものがSPC法ですから、その目的は資産の流動化であり、そのために設立される会社も会社法上の会社ではなく、社団法人なのです。つまり、SPC法はSPC設立のための法律ではありません。
資産の流動化とは、一連の行為として、TMKが資産対応証券の発行もしくは特定借入れにより得られる金銭を持って資産を取得、または信託会社その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、資産対応証券、特定借入れ及び受益証券にかかる債務または出資についてその債務の履行をし、または利益の配当及び償却のための取得または残余財産の分配を行うことをいいます(SPC法2条2項)。
簡潔に言うと、債権や不動産等の資産を有する者が、特定の資産を保有するためにSPVを作り、そのSPVに資産を譲渡し、その資産が生み出す将来のキャッシュフローを原資として資金調達を行うということです。
この特定の資産を保有する者をオリジネーターといい、また、資産の流動化のうち、資産を有価証券化して行うものを資産の証券化といいます。
▷SPC法と会社法との違い
SPC法は、その名のとおり、資産の流動化のための法律であり、SPC法によって設立する法人は社団法人・TMKです。
一方、会社法は株式会社や合同会社・合資会社・合名会社等の会社の設立、組織、運営及び管理について定める法律です。SPCは特定の目的のために設立される会社ですから、その設計により適用される法律は異なることになります。
SPCの設立・登記・手続
SPCは特定の目的のために設立された法人ですから、その制度設計により、どのような法人を設立するかは変わっていきます。
資産流動化のためにSPC法によるTMKを設立する以外に、M&Aでは合同会社・株式会社や匿名組合を設立するのが一般的です。SPCでも会社法上の会社を設立するのであれば、通常の株式会社や合名会社・合同会社・合資会社を設立するのと同じですし、匿名組合の場合には契約のみで設立できます。
ただし、匿名組合の場合には契約により損益や金銭の分配についても決定してしまうので、弁護士の関与があるのが一般的ですが、会計及び税務上の確認も十分に行う必要があります。
TMKを設立する場合も、SPC法上の届出、流動化計画作成等、SPC法上の手続を行う必要があります。
SPCのスキーム
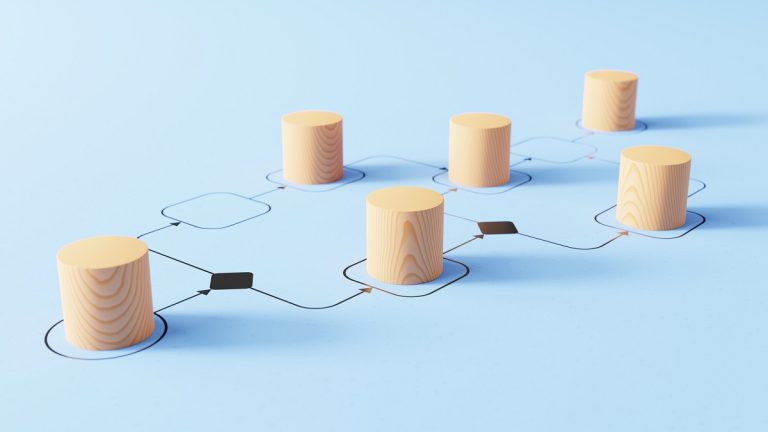
SPCを設立するスキームとしては主に3種類が挙げられます。
1)TMK(特定目的会社)
2)GK-TK(合同会社匿名組合)
3)REIT(不動産投資信託)
1)TMK(特定目的会社)
TMKはTokumei Mokuteki Kaisha(特定目的会社)の頭文字を指し、SPCとしてTMKを設立、不動産や信託受益権を取得し運用するスキームになります。
TMKはSPC法を根拠としており税制の優遇を受ける事が可能ではあるものの、事業範囲は定められており限定的になっています。
▷関連記事:特定目的会社(TMK)とは?設立の手順やメリット・デメリットについて解説
2)GK-TK(合同会社-匿名組合)
GK-TKはGodo Kaisya(合同会社)とTokumei Kaisya(匿名組合)の頭文字を指し、設立が容易かつ管理するコストも低い事もあり、SPCでよく利用されるスキームです。
SPCとして合同会社を設立し、投資家から匿名組合を通じた出資や金融機関からの借入を受け、不動産や信託受益権を購入し、その利益から匿名組合員への分配や金融機関への返済を行ないます。
3)REIT(不動産投資信託)
REITはReal Estate Investment Trust(不動産投資信託)の略となり、投資家から調達した資金を不動産へ投資、その利益で投資家への配当金や金融機関への返済を行ないます。
REITスキームを行なう際には資産運用会社(アセットマネージャー)に資産運用、資産保管会社に資産の保管を委託するケースがあります。
SPCを導入するメリット・デメリット

資産流動化の場面で、なぜSPCが必要とされるのか、メリットとデメリットをみてみましょう。
▷SPCのメリット
資産流動化は、ある資産についてオリジネーター(M&Aの案件の発掘や提案業務をおこなう人)側ではそれを手放してもよく、投資家側では資産価値を背景とした、いつでも譲渡可能な債権や証券が欲しいという状態を実現するために行われます。
資産を流動化した場合には、資産価値の構成要素を債権・証券として分離して保有するという効果が生じ、経営者の交代等のマネジメントや、他の事業上のリスクを含めた企業リスクから分離されます。そのため、当該資産から生じるキャッシュフローを含めた資産価値の変動のみを引き当てる証券に対するニーズがあり、資金調達が可能になるのです。
企業リスクを投資家が監視するには相当な労力を必要としますが、費用がかかり、その監視も限度があります。つまり、その監視費用がSPCの組成費用を上回る場合に投資家におけるメリットがあります。
たとえば、オリジネーターが自らある資産を担保とする担保付社債を発行する場合には、オリジネーターの企業リスクから分離できません。また、投資家が当該資産を購入して直接管理する場合、自分で管理・処分しなければなりません。これに対して、関係者の倒産等のリスクから影響を受けないSPCにより資産価値を証券化すれば、投資家はこれらのリスクから逃れることができます。
さらに、SPCを利用する場合には、資産をオフバランス化することが可能です。オフバランス化とは、会社の貸借対照表(B/S)から不動産などの資産を切り離すことをいいます。SPCを利用すると、オリジネーターの資産をSPCが取得することで、オリジネーター側でオフバランス化がされます。さらに連結対象から外れることで、結果として自己資本比率が改善されます。
しかし、自己資本比率が改善してもROEは低下することもあり、事業リスクは低くなるものの利回りが悪くなることがあります。その意味でも制度設計は重要です。
加えて、SPCは海外でも設立が可能ですから、適用したい国において設立することでその国の法制度を利用することができます。ただし、TMKは外国法人としての設立ができないため、利用はできません。
以上の利点をまとめると次のようになります。
1.関係者の企業リスクから分離された債権への転換や証券の発行が可能
2.オリジネーター等関係者の固有の財産と計算等の混同の防止が可能
3.設立国の法制度の利用が可能
▷SPCのデメリット
デメリットとしては、制度設計を失敗すると想定した利益を得られなかったり、設立や運用にコストがかかることがあります。
また、第三者からの出資がある場合には、利益を分配する必要もあります。
さらに、M&AにおいてSPCが調達した資金を用いて買収対象会社の株式を取得する場合、株式取得後SPCと対象会社が合併しますが、そうすると調達した資金にかかる債務等が合併後の対象会社に残ることになります。
そのため、この債務等についても事前に十分な検討をしておく必要があります。
M&AにおけるSPCの利用

これまでもみてきたとおり、M&AにおいてSPCを利用するのは、買収しようとする会社においてはSPCが資金調達を行うため、自らは買収にかかる資金調達のリスクを負わなくてよいというメリットがあります。
これにより、少ない負担・リスクでM&Aを実行することができるのです。
SPCはLBOの手段としてもよく利用されます。LBOとは、SPCが金融機関から高利率で買収資金を借り、その資金で買収した上で、対象会社と合併し、当該買収資金を金融機関に返済していくものです。
LBOにおいては、買収後合併後の会社が金融機関に借り入れを返済することが前提であり、買収する側であるSPCは対象会社の株主全員から株式を取得するためにプレミアを上乗せした金額を提示するのが一般的です。そのため、対象会社の株主としても高額で売却することが可能です。金融機関としては、回収できない可能性がある一方で、高利率での貸し付けを行うことができます。
このLBOにおいても、買収する側は手元の資金が少ない状態でもM&Aが可能になるのです。しかし、LBOは買収後の借入金返済が過大な負担となる可能性があるため、十分な注意が必要です。
▷関連記事:LBOとは?MBOとの違いと仕組み・手法から事例まで解説
SPCを活用した事例
実際にSPCが用いられた事例を紹介します。
ソフトバンクグループの事例
2021年9月に、ソフトバンクグループは愛知県と「愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業」の基本協定を締結しました。
その後、ソフトバンクグループは事業主体となるSPCとして「STATION Ai株式会社」を設立しました。
STATION Ai株式会社が主体となる事業は、ユニコーン企業や人材育成の拠点として、SPCを活用して資金調達やベンチャー企業が共に成長できる環境を整えることを目的としたものであると考えられます。
ホテルオークラ東京の事例
2016年6月に、新日鉄興和不動産不動産株式会社と大成建設株式会社が、株式会社ホテルオークラ等と設立したSPCSを通じて「ホテルオークラ東京本館建替計画」に際したオフィス賃貸事業を推進することを発表しました。
新日鉄興和不動産不動産株式会社と大成建設株式会社は、SPCからオフィスの企画やテナント募集、完成後の運営といったオフィス事業全般を受託していました。
吉本興業の事例
2009年に、吉本興業株式会社に対し、上場を廃止する目的でSPCを用いたM&Aが実施されました。
買収したのはソニーの元会長である出井伸之氏が代表を務める投資会社「クオンタム・エンターテイメント株式会社」で、吉本興業を買収するために作られた会社なのでSPCに該当します。
クオンタム・エンターテイメントにはフジテレビや日本テレビなどのテレビ局、電通、ソフトバンク、ヤフーなどが出資しており、メガバンクなどからも多額の資金を借り入れています。クオンタム・エンターテイメントはこれらの資金を用いて、TOBにより吉本興業を買収しました。吉本興業側もこのTOBを歓迎しました。
その後、クオンタム・エンターテイメントと吉本興業は合併し、現在は吉本興業ホールディングス株式会社という社名になっています。
まとめ
SPC法は、SPC全体を定めた法律ではなく、SPCの中でも資産の流動化について定める法律であり、SPC法により設立されるのは会社法上の会社ではなく、特定目的会社(TMK)という社団法人です。SPCは特定の目的のために設立された法人一般を指し、その目的達成のためにさまざまな組織を設立することになります。
当該目的を達成するために最も適した設計をする必要があり、そのメリットを活かすためにも、弁護士や公認会計士等の専門家との十分な検討が必要となるでしょう。
※この記事は執筆当時の法令等に基づいて記載しています。
