
会社の一部事業の切り離しや親族への事業承継など、事業縮小のための手法は様々な方法が考えられます。その中で、事業規模や移転する事業の範囲などによっては「営業譲渡(事業譲渡)」という手法が適している場合があります。
本記事では、営業譲渡(事業譲渡)の基本的な知識から、類似のM&A手法である株式譲渡・会社分割との違いや、売手及び買手企業にとってのメリット・デメリットについて解説していきます。
営業譲渡(事業譲渡)を検討されている方は、ぜひご一読ください。
上場企業に負けない 「高成長型企業」をつくる資金調達メソッド
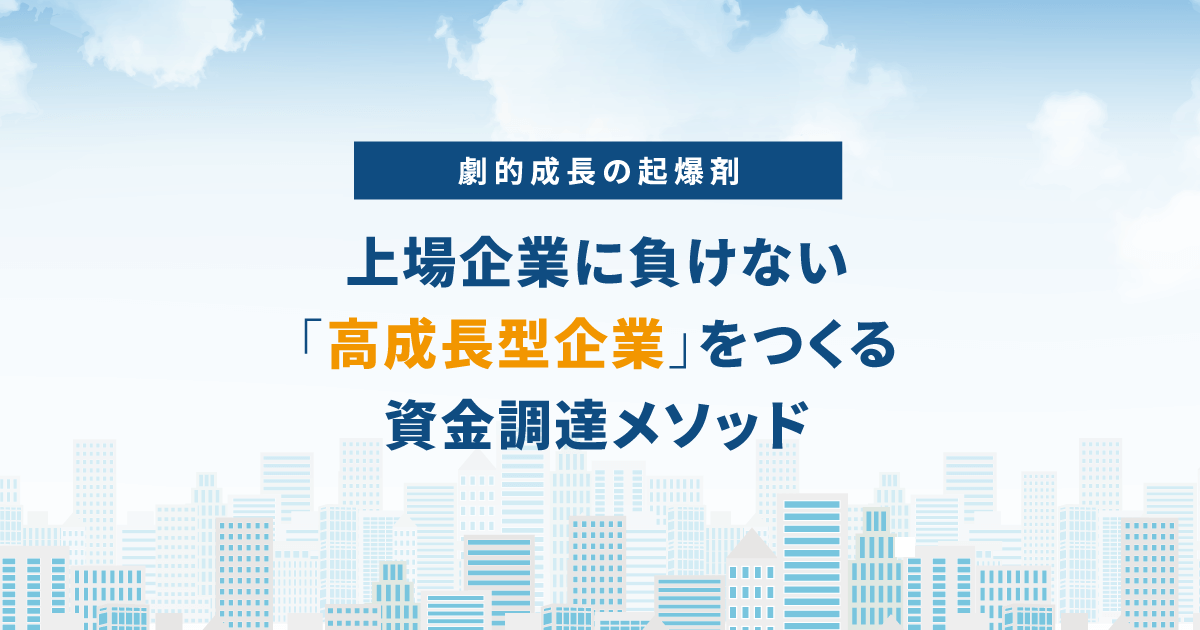
本資料では自社をさらに成長させるために必要な資金力をアップする方法や、M&Aの最適なタイミングを解説しています。
・縮小する日本経済市場を生き抜くために必要な戦略とは?
・まず必要な資金力を増強させる仕組み
・成長企業のM&A事例4選
M&Aをご検討の方はもちろん、自社をもっと成長させたい方やIPOをご検討の方にもお役立ていただける資料ですので、ぜひご一読ください。
目次
営業譲渡とは

営業譲渡とは、会社全体ではなく必要な事業の資産・負債のみを売買するM&A手法です。
よく似たものに「株式譲渡」がありますが、営業譲渡は対象となる事業を選択できるなどの点で、株式譲渡とは異なります。
営業譲渡は、有形固定資産(土地や建物など)や流動資産(売掛金・在庫など)だけでなく、営業権 (のれん) や人材、ノウハウといった無形の資産も譲渡の対象です。
営業譲渡において事業を移転する際の手続きは複雑で、資産・負債の移転の際は個別の移転手続きが必要です。また不動産が譲渡の対象となる場合は、移転登記手続きも必要となります。
営業譲渡のための手続きによってコストが増大するデメリットも想定されるため、事業譲渡の手法を選択するか否かは、慎重かつ他のM&Aスキームと比較して検討することが重要です。
営業譲渡と似た用語の解説
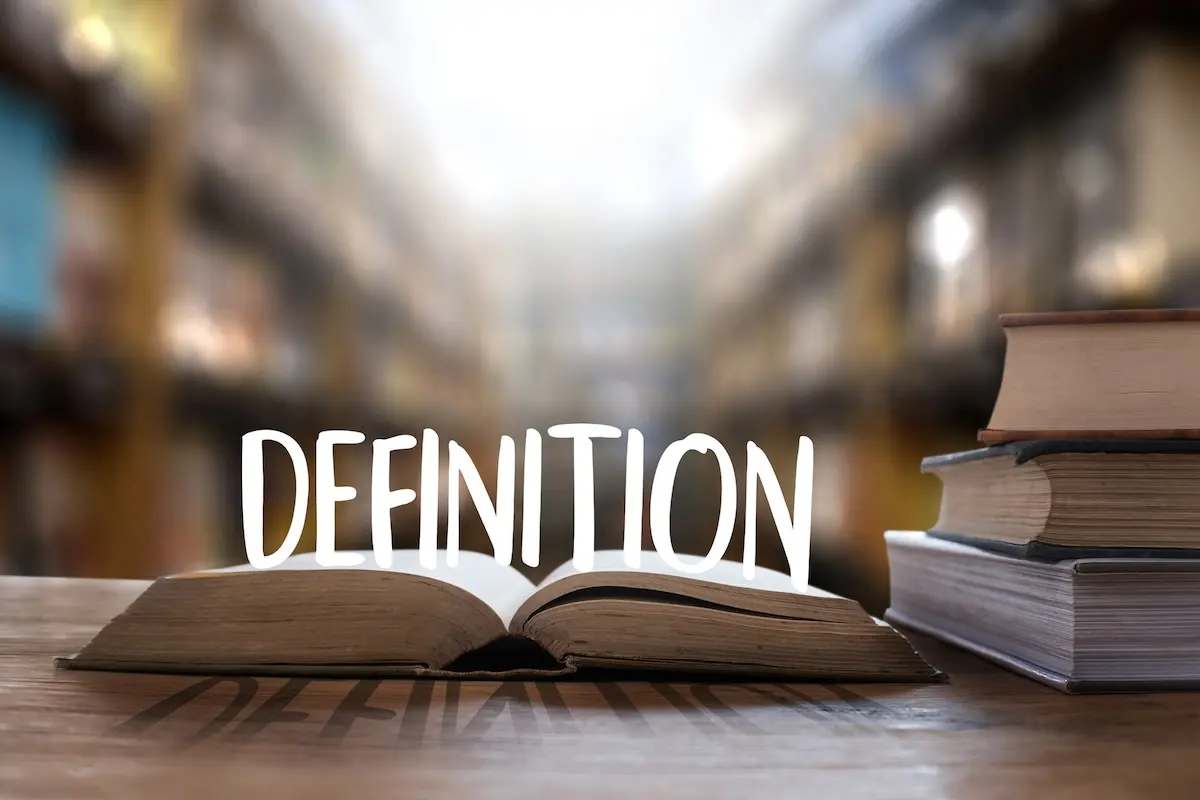
事業譲渡と混同しやすい組織再編の各手法について解説します。
営業譲渡と事業譲渡の違い
営業譲渡の他に「事業譲渡」という名称を聞くこともあり、どんな違いがあるのか疑問に感じる方は多いでしょう。
結論から言うと、営業譲渡と事業譲渡は、どちらも同じ内容を指します。
2006年(平成18年)に会社法が施行され、「営業譲渡」は「事業譲渡」となりました。
会社法か旧商法上の規定かどうかで呼称が変わりますが、内容はどちらも変わりません。
ただ、商法が適用される譲渡の場合は、今でも営業譲渡と呼ばれています。
事業譲渡の詳細については以下の記事でも解説しておりますので、ぜひご参照ください。
▷関連記事:事業譲渡とは?株式譲渡との違いやメリット・デメリットを徹底解説
営業譲渡(事業譲渡)と会社分割の違い
営業譲渡(事業譲渡)と会社分割は、いずれも事業縮小のための M&A で適用される手法という点で共通しています。一方で、事業を移転先へ引き継ぐ方法として、営業譲渡(事業譲渡)は「個別承継」、会社分割は「包括承継」という点で異なります。
「個別承継」とは、資産・負債や従業員などの権利義務について個別の移転手続きを経て承継させることをいいます。例えば、資産については売買契約を、従業員については雇用契約を別途締結し直す必要があるため、事業の移転手続きの負担が大きくなります。
これに対して「包括承継」の場合は、資産・負債や契約関係などに関する個別の移転手続や承諾を得ることなく、買い手側に包括的に移転できる手法であるため、事業譲渡に比べて法的手続きが容易に行えます。
営業譲渡(事業譲渡)と株式譲渡の違い
営業譲渡(事業譲渡)と株式譲渡は、いずれも会社の組織再編において幅広く用いられるM&A手法です。
両者には譲渡の直接の対象が「事業」であるか「株式」であるかという違いがあります。また買い手側に権利義務を引き継ぐ手法として、営業譲渡(事業譲渡)は「個別承継」に該当し、 株式譲渡は「包括承継」という点で異なります。
営業譲渡(事業譲渡)のメリット

営業譲渡(事業譲渡)は事業の一部を譲り受けるものなので、株式譲渡に比べるとリターンが少ないように思えます。
しかし営業譲渡(事業譲渡)には、株式譲渡にはない他のメリットがあります。以下では、営業譲渡(事業譲渡)のメリットを売却企業・買収企業の双方の観点から解説します。
売却企業側のメリット
営業譲渡(事業譲渡)は、売却企業側にとって以下のメリットがあります
特定の事業のみを売却できる
営業譲渡(事業譲渡)では、手放したい特定の事業だけを売却可能です。自社で継続したい事業がある場合は、手放さずに残しておくことが可能です。株式譲渡の場合、継続したい事業もすべて譲らなければいけないため、この点では事業譲渡の方が優れているといえます。
事業の中に負債があっても買い手を見つけやすい
営業譲渡(事業譲渡)は一部の事業のみが対象なので、買い手が欲しがらない負債を譲渡の対象外にすることができます。そのため、買い手がほしがる事業のみを売却することができます。
譲渡代金を元手に新規事業を起こせる
営業譲渡(事業譲渡)により獲得した資金を新規事業への投資に回すことで、さらなる会社の成長へつなげていくことが可能です。
会社経営を継続できる
事業を譲渡した後も、残った事業で会社経営を継続できます。
買収企業側のメリット
営業譲渡(事業譲渡)は、買収企業側にとって以下のメリットがあります。
負債を引き継がなくて良い
買い手側は必要な資産だけを選べるので、営業譲渡(事業譲渡)を行う時点では予見できない偶発債務や簿外債務などの負債の引継ぎを回避できます。
対象事業の範囲を選べる
営業譲渡(事業譲渡)では、利益が見込める事業、欲しい人材など、譲り受ける事業の範囲を選択可能です。自社に不要なものを引き継ぐ必要はありません。
のれん相当額の償却、有形固定資産の減価償却等の節税に繋がる
有形固定資産の減価償却やのれん代相当額の償却を、譲受企業側の「損金」として計上できます。譲受企業側の損金にすることで課税所得を減額できるため、節税につながります。
営業譲渡(事業譲渡)のデメリット
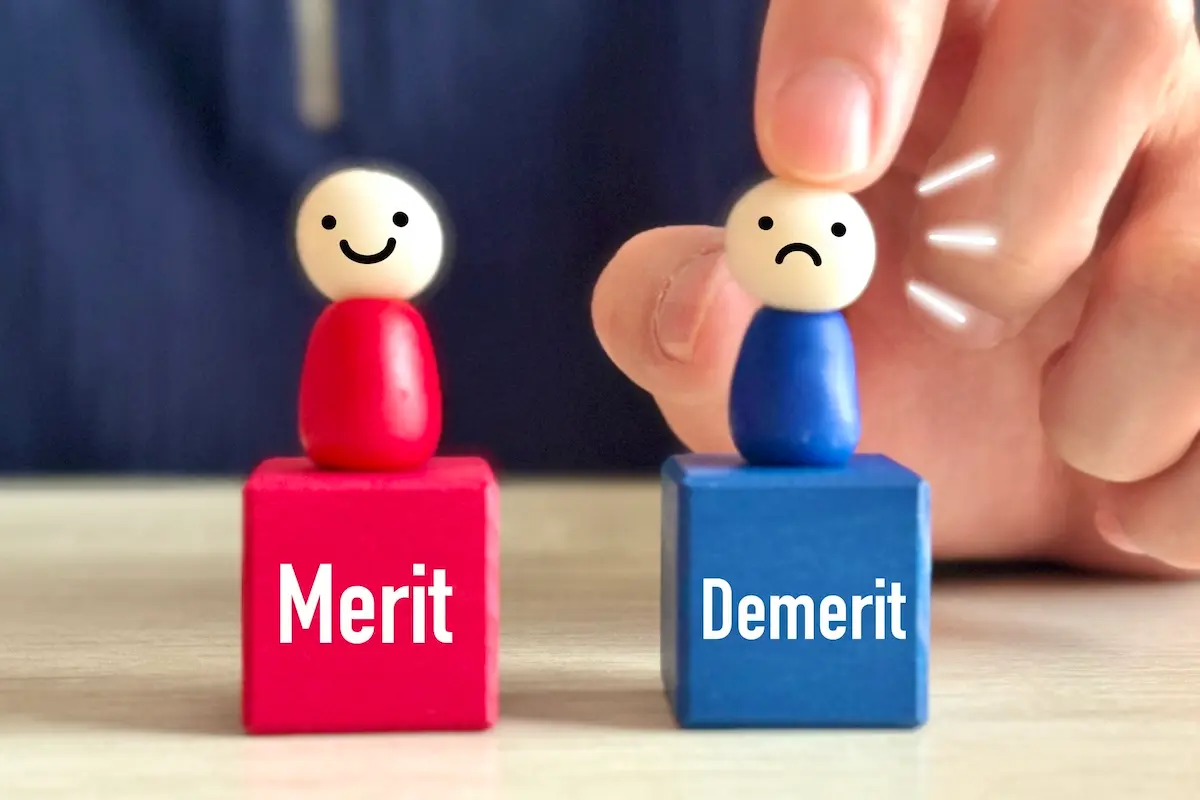
営業譲渡(事業譲渡)を行う場合はメリットだけでなく、デメリットも把握しておくことが重要です。以下では、営業譲渡(事業譲渡)のデメリットについて解説します。
売却企業側のデメリット
営業譲渡(事業譲渡)における売却企業側の主なデメリットは、以下の通りです。
競業禁止義務の制約を受ける
会社法の規定により、営業譲渡(事業譲渡)を行った後20年間は、同一の区市町村や隣接する区市町村では、譲渡した事業と同一の事業を行うことが禁止されています。営業譲渡(事業譲渡)後も同じ事業を行う予定がある会社は、注意が必要です。
譲渡益には法人税が課税される
譲渡益が発生した場合、譲渡益に対して法人税が約30%課税されます。譲渡益が大きいほど税負担が増すため、税務面でのデメリットといえます。
買収企業側のデメリット
営業譲渡(事業譲渡)における買収企業側の主なデメリットは、以下の通りです。
事業譲渡の手続きが煩雑
営業譲渡(事業譲渡)は通常手続きが煩雑になります。例えば、従業員の契約を再度交わす必要が生じたり、行政からの許認可も再度取得したりしないといけません。このように手続きに手間や時間がかかるのは、買収企業側のデメリットといえます。
顧客や従業員、取引先の離反リスク
営業譲渡(事業譲渡)は、顧客・従業員・取引先との契約関係を一度リセットした上で、再締結が求められます。再締結をきっかけに離反に繋がる恐れがあり、従業員や取引先が事業譲渡に反対することも考えられます。営業譲渡(事業譲渡)の失敗や新たなトラブルの原因になることもあるため、事前に従業員との連携や緻密な協議を重ねておきましょう。
営業譲渡の注意点
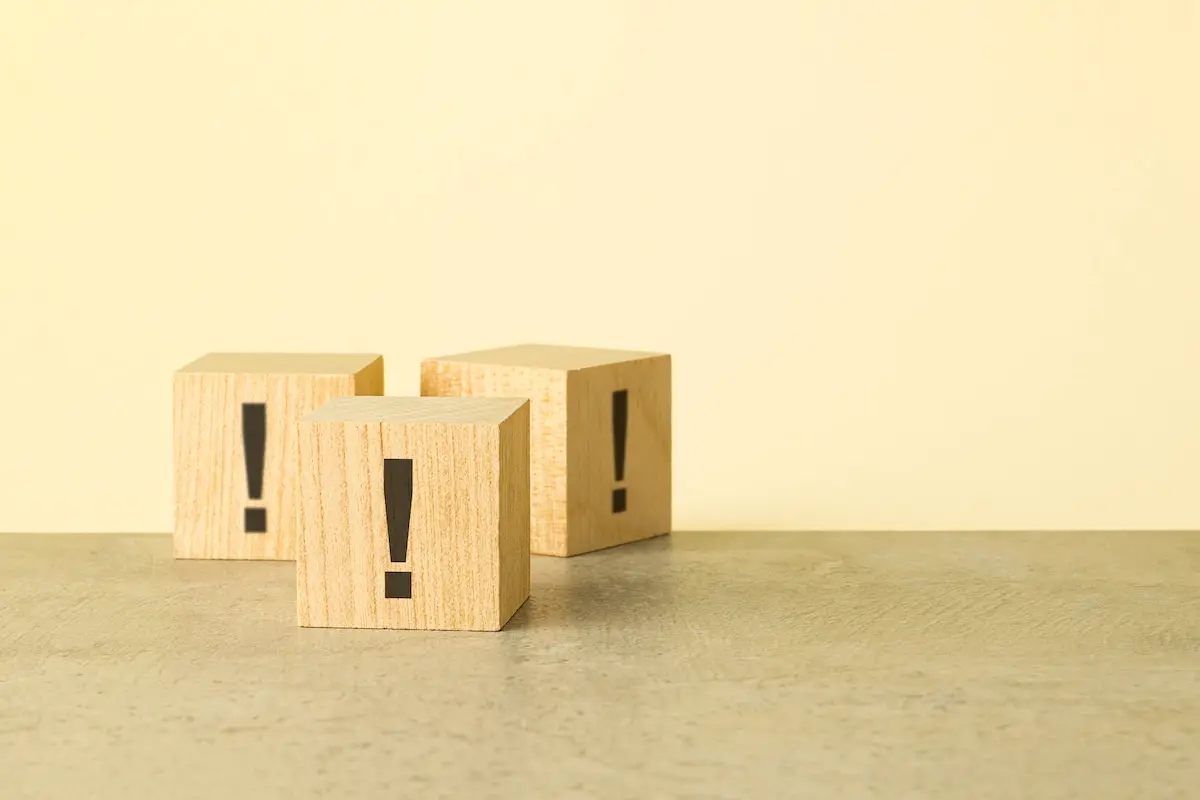
営業譲渡(事業譲渡)では、売却企業・買収企業ともに注意すべき点があります。
債務や税務・税金に関するリスクなどがあるため、事前に整理した上で営業譲渡(事業譲渡)の準備を進めるようにしましょう。
ここでは、売却企業・買収企業それぞれの注意点について解説します。
売却企業側の注意点
営業譲渡(事業譲渡)を行うにあたって、売却企業は以下の注意点があります。
債務面でのリスク
営業譲渡(事業譲渡)を行う会社が債務超過に陥っている場合は、注意が必要です。
営業譲渡(事業譲渡)を行うことにより、会社の収益力低下と共に債務の返済能力が低下する恐れがあります。その結果、営業譲渡(事業譲渡)そのものが差し止められるケースもあります。そのため、経営不振の企業が営業譲渡契約を結ぶ際は、差し止めのリスクも考慮することが重要です。
譲渡益にかかる法人税
事業譲渡によって譲渡益が発生すると、法人税が課税されます。法人税率は30%程度かかるため、資金繰りなど税負担についてもあらかじめ対応策を検討しておきましょう。
買収企業側の注意点
営業譲渡(事業譲渡)を行うにあたって、買収企業には以下の注意点があります。
事業継承できないか検討する
営業譲渡(事業譲渡)を行う前に、事業継承できないかも含めて検討しましょう。親族や従業員に継承できれば、事業譲渡しなくてもよい場合があります。
事業継承であれば、株主や債権者など関係者の理解も得やすいため、後継者を探している場合は、事業継承の手法も検討しましょう。
顧客・取引先との契約関係が白紙に戻る
営業譲渡(事業譲渡)を行うと、顧客や取引先との契約関係が白紙になります。そのため、再度契約締結の手続きが必要となり、事業開始までに時間がかかります。営業譲渡(事業譲渡)には、このような手間や時間がかかることも認識しておきましょう。
営業譲渡の手続きの流れ

営業譲渡(事業譲渡)を決めたら、取締役会での承認が必要となります。承認が得られれば、買い手の選定・交渉に進みます。交渉がまとまったら、基本合意契約を締結し、デューディリジェンス(企業調査)を行います。
企業調査で問題がなければ、取締役会での決議を経て営業譲渡(事業譲渡)契約を締結します。効力発生日が到来すると、契約の手続きは一旦完了です。
ただし、事業を完全に引き継ぐために経営の方法をすり合わせながら、全ての課題が解決するまで引き続き買収先企業との協力が必要です。事業の引き継ぎが完全に終われば、手続きは完了です。
営業譲渡(事業譲渡)契約書に記載する項目
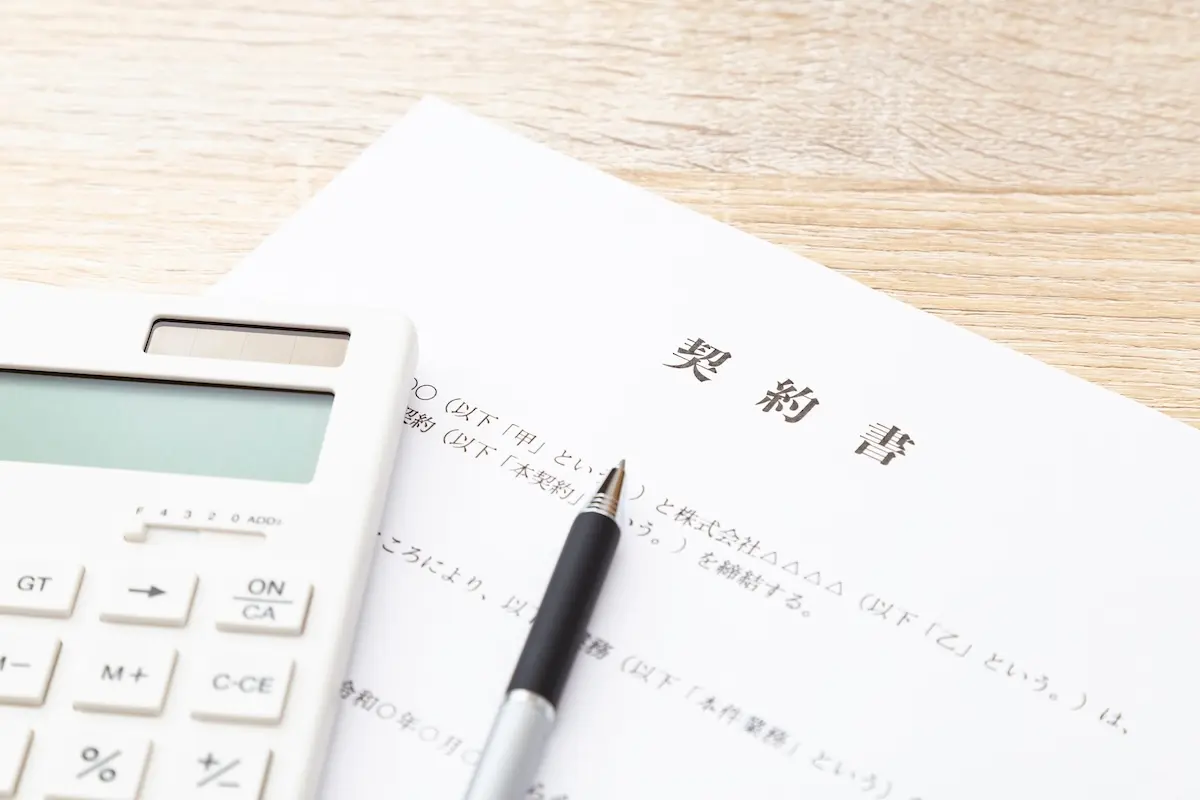
営業譲渡(事業譲渡)契約書に記載する項目は、複数あります。記載が必要な項目については下表を参照ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 譲渡対象となる事業の特定 | 営業譲渡(事業譲渡)の対象となる資産と負債を特定できるように記載 |
| クロージング日 | 譲渡実行日 |
| 譲渡金額など | 営業譲渡(事業譲渡)で支払われる金額や支払い方法 |
| 公租公課の支払い | 公租公課(国や公共団体が国民に課す租税称)の支払いをいつ売り手に切り替えるのか? |
| 従業員の取り扱い | 従業員の待遇(雇用を続けるのか?退職金をどうするのか?等) |
| 表明保証 | 財務や法務の内容が真実かつ正確であると保証するもの。違反した場合は補償を請求できる |
| 譲渡企業の義務 | 譲渡企業に善管義務(善良な管理者として通常期待される注意義務)を設定する |
| その他の事項 | その他の事項も付加することも可能 |
記載する項目が多いので、記入漏れがないように注意しましょう。
営業譲渡(事業譲渡)契約書については、以下の記事で詳しくまとめています。
▷関連記事:事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説
営業譲渡(事業譲渡)後の償却資産の減価償却

営業譲渡(事業譲渡)で引き継いだ減価償却資産は、時価で受け入れます。時価が上昇している場合は、買収対象会社による減価償却後の帳簿価額を基礎に減価償却費を計上するよりも、減価償却費を多く計上できます。
また耐用年数も通常の法定耐用年数ではなく、より短い期間である中古資産の耐用年数を適用可能となるため、この点でも減価償却費を多く計上できます。
さらに、譲渡対象の事業に関する純資産(資産と負債の差額)を上回る譲渡対価を支払った場合は、「のれん」という税務特有の資産調整勘定が発生します。この「のれん」は、5年の償却期間にわたって損金計上が可能です。のれんについては以下の記事で詳しく解説しています。
▷関連記事:M&Aで必ず知っておくべき「のれん代」を徹底解説
営業譲渡(事業譲渡)後の税務処理
営業譲渡(事業譲渡)後の税務処理について、注意すべき点がいくつかあります。具体的には、下表の通りです。
| 法人税 | 売却価格が簿価総額を上回っている場合、差額が課税所得となり法人税が課税される。 売却価格が簿価総額を下回る場合には、課税所得はマイナスになる。 |
| のれんの調整勘定(資産・負債) | 資産調整勘定や差額負債調整勘定は、60か月に渡って月割で償却していく。 会計上ののれんのように、最長20年以内の任意期の期間で償却する方法ではない。 |
| 減価償却資産 | 耐用年数の計算は見積もりが難しいケースもある。その場合は以下の計算式を使う。 ・法定耐用年数を超えていない:「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」で算出。 ・法定耐用年数を超えている:「法定耐用年数×20%」で算出。 |
| 消費税がかかる取引とかからない取引 | 消費税の課税対象:有形固定資産や棚卸資産・無形固定資産、のれんなどの資産に関する取引。 非課税となる取引:土地や有価証券、金銭債権の譲渡。 |
| 非課税売上となる取引 | 土地や有価証券、金銭債権の譲渡。 課税売上割合を下げる要因になるので注意。 |
| 流通税がかかる取引 | 不動産の所有権移転登記で発生する「登録免許税」や「不動産取得税」といった税金。 登録免許税は「固定資産税評価額×2%」不動産取得税は「固定資産税評価額×4%」で算出する。 |
上記のように会計上の処理と税務上の処理が一致しない場合があるので、専門家のサポートを受けるのも有効です。
【Q&A】営業譲渡(事業譲渡)のよくある質問

ここでは、営業譲渡(事業譲渡)に関連するよくある質問について紹介します。
営業譲渡(事業譲渡)とはどういう意味ですか?
営業譲渡(事業譲渡)とは、会社全体ではなく特定の事業における資産・負債のみを売買するM&A手法です。詳細は記事内「事業譲渡とは」をご覧ください。
営業譲渡(事業譲渡)とM&Aの違いは何ですか?
営業譲渡(事業譲渡)はM&A手法の一つですが、M&Aとは根本的な位置付けが異なります。
まず、営業譲渡(事業譲渡)は会社における「事業の売却」を意味します。金額規模が大きくなる場合が多いですが、あくまで会社が通常行う「売買取引」に近しいものといえます。
一方でM&Aは、会社分割、株式譲渡など数多く存在するM&A手法のいずれかを用いた「経営戦略」を意味します。両者は「取引」と「戦略」という点で位置付けが異なるものと考えられます。
営業譲渡(事業譲渡)のメリット・デメリットは?
営業譲渡(事業譲渡)のメリットとして、売却企業側には「特定の事業のみを売却できる」「事業の中に負債があっても買い手を見つけやすい」といった点があり、買収企業側には「負債を引き継がなくて良い」「対象事業の範囲を選べる」という点が考えられます。
一方で、営業譲渡(事業譲渡)のデメリットとして、売却企業側には「競業禁止義務の制約を受ける」「譲渡益には法人税が発生する」といった点があり、買収企業側には「事業譲渡の手続きが煩雑」「顧客や従業員、取引先の離反リスク」という点が考えられます。
詳細は記事内「事業譲渡のメリット」及び「事業譲渡のデメリット」をご覧ください。
まとめ:M&Aによる事業承継は早めに検討
営業譲渡(事業譲渡)は会社内の残したい事業と切り離したい事業を個別に選択できるため、事業の「選択と集中」という目的を達成させる点で優れた手法です。また、営業譲渡(事業譲渡)によって得た資金を元手に、新規事業へ投資することもできます。
一方で、手続きの面で時間と手間がかかる点にも注意が必要です。会社法上、原則として株主総会の決議を要するため、株主総会で承認をもらうための事前準備やスケジュール調整などが発生します。
このほか、譲渡の対象となる債務については、個別に債権者の同意を得る必要が生じたり、また個々の従業員の雇用契約の見直しなど、手続きの面で様々な負担が増大したりします。
事業譲渡の手続きをスムーズに進めていくためには、事業譲渡の事前準備から手続完了までの計画やスケジュールを早期かつ余裕をもって検討、策定しておくことが重要です。
営業譲渡(事業譲渡)に関して疑問がある場合は、fundbookにご相談ください。経験豊富なアドバイザーが在籍しており、営業譲渡(事業譲渡)についてサポートいたします。
初回相談は無料で依頼可能です。営業譲渡(事業譲渡)を検討している場合は、ぜひお問い合わせください。

椎名 潤
