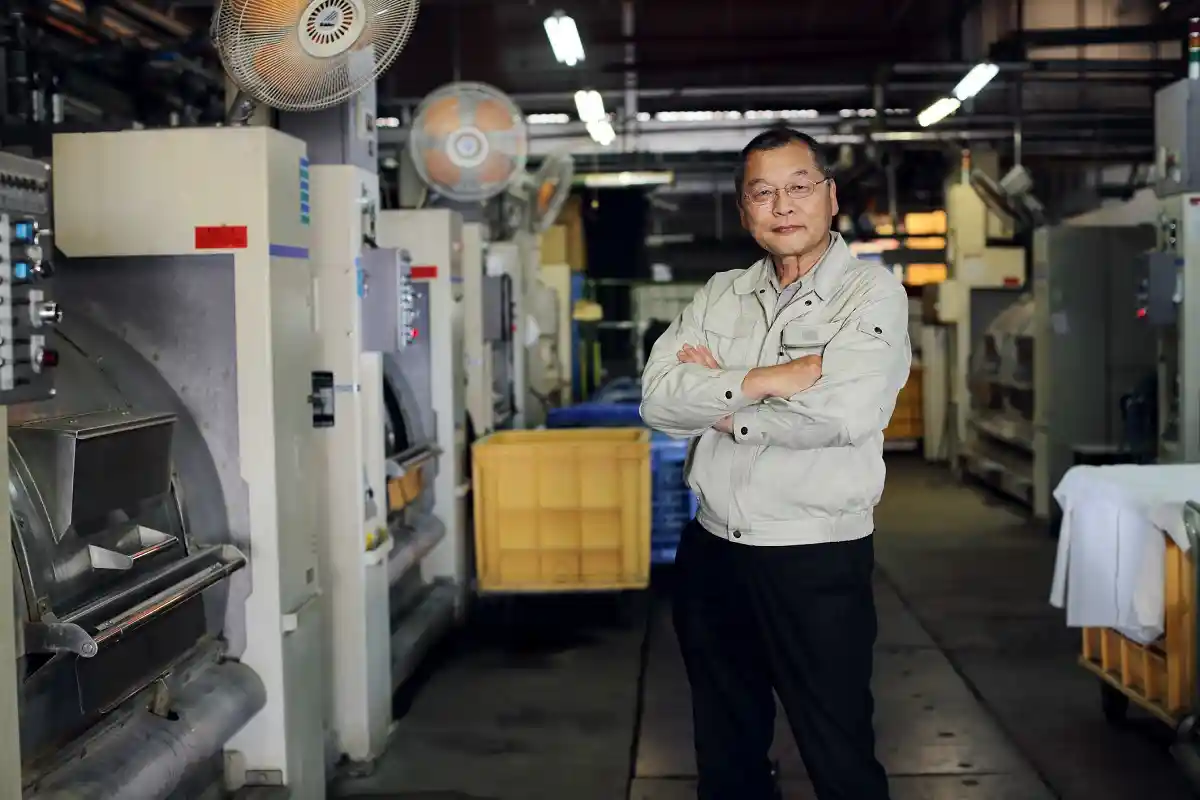
製造業は日本経済を支える代表的な産業ですが、一方で、業界全体が抱える課題がいくつかあります。
昨今は、製造業界が抱える課題の解決策としてM&Aが活用されるケースも多く、製造業に携わる経営者の中にはM&Aを検討している方もいるのではないでしょうか。
M&Aを実施する際は、業界のM&A動向や実施することで得られるメリット、成功させるためのポイントなどを把握しておくことが大切です。
本記事では、製造業のM&Aについて動向やメリット、成功事例、成功させるためのポイントを解説します。
年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法
・M&Aの進め方や全体の流れ
・成約までに必要な期間
・M&Aに向けて事前に準備すべきこと
会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!
目次
製造業とは
製造業は「有機または無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所」と定義されています。
具体的には以下の2つの業務を行う事業所(工場や作業所など)のことを指します。
・新たな製品の製造加工を行う
・新たな製品を主として卸売する
新たな製品の製造加工を行う事業所の観点からすると、単に製品の選別や包装の作業を行う事業所は製造業には含まれません。
他方、完成された部品の組み立て作業を行う事業所は製造業に含まれます。
また、卸売業者や小売業者に販売したり産業用使用者(工場や官公庁、学校、ホテルなど)に製品を大量または多額に販売したりなど、卸売の条件を満たしている事業所であることも必須です。
▷製造業の種類
総務省の「日本標準産業分類」によると、製造業は「大分類E-製造業」に分類され、さらに、食品製造業や飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、鉄鋼業などをはじめとする24種類の中分類に分けられます。
| 製造業の種類 ・食料品製造業 ・飲料・たばこ・飼料製造業 ・繊維工業 ・木材・木製品製造業(家具を除く) ・家具・装備品製造業 ・パルプ・紙・紙加工品製造業 ・印刷・同関連業 ・化学工業 ・石油製品・石炭製品製造業 ・プラスチック製品製造業(別掲を除く) ・ゴム製品製造業 ・なめし革・同製品・毛皮製造業 ・窯業・土石製品製造業 ・鉄鋼業 ・非鉄金属製造業 ・金属製品製造業 ・はん用機械器具製造業 ・生産用機械器具製造業 ・業務用機械器具製造業 ・電子部品・デバイス・電子回路製造業 ・電気機械器具製造業 ・情報通信機械器具製造業 ・輸送用機械器具製造業 ・その他の製造業 |
▷製造業界の市場規模
経済産業省によると、2022年度時点における製造業が日本のGDPに占める割合は19.4%で、全体の約2割を占めています。
2022年の製造業全体の営業利益は約19.5兆円、2023年は約22.6兆円と増大傾向であることからも、製造業は日本全体の経済基盤を支える重要な産業であることが分かります。
出典:経済産業省「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)
出典:財務省「年次別法人企業統計調査(令和5年度)結果の概要」
製造業界の経営課題
日本経済の中心産業である製造業ですが、業界全体として改善に取り組むべき課題がいくつかあります。
以下では、製造業界の主な経営課題を4つ解説します。
▷物価やエネルギー価格高騰による利益圧迫
製造業は、近年の急激な物価高騰による影響を多大に受けています。経済産業省が発表した「2024年版ものづくり白書(ものづくり基盤技術振興基本法第8条に基づく年次報告)」の中の「事業に影響を及ぼす社会情勢の変化に関する調査」によると、事業に影響を及ぼす大きな要因として「原材料価格(資源価格)の高騰」と「エネルギー価格の高騰」が報告されています。
しかし、原材料価格やエネルギー価格の値上がり分を販売価格に転嫁している事業者は少なく、利益圧迫を引き起こしているケースが少なくありません。
2023年度時点での製造・販売する製品や部素材の原材料高騰分の価格転嫁割合をみると、約30%の事業者が、適正価格に対して50%以下しか価格転嫁できていないと答えており、適正な価格転嫁ができていない企業が一定数いることが分かります。
価格転嫁が進まない主な要因としては、大企業、中小企業ともに「取引先からの理解が得にくい」「取引先との交渉力が弱い」を挙げる割合が多いです。
▷少子高齢化による人材不足
日本全体の問題でもある少子高齢化は製造業界にも影響を与えており、製造業では人材不足が深刻な問題です。事実、2023年度の製造業就業者数は1,055万人であり、2002年からの約20年間で約150万人も減少しています。さらに、34歳以下若年層の就業者数は125万人減少しています。
若年層の就業者数が減少する一方、高齢就業者は約20年前の2002年に比べて30万人増加していることから、製造業界でも高齢化が進んでいることがわかります。
また、経済産業省が過去に行ったアンケートでは、94%の企業が「人材確保に課題がある」、さらに3割強の企業においては「ビジネスに影響が出ている」と回答していることからも、人材の確保は製造業の大きな課題といえるでしょう。
▷無形固定資産への設備投資が不足している
新型コロナウイルスの影響もあって、製造業では2020年まで設備・環境投資を見送る企業が多く見られました。
2020年前半は業界全体の設備投資額が大幅に落ち込んでいたものの、以降は設備投資が増加傾向にあり、製造業でも徐々に設備投資が進んでいます。製造業の設備投資では、有形固定資産への投資は高い水準であるのに対し、無形固定資産への投資は半数以上の企業が実施していない状況です。
無形固定資産には、業務効率化やコスト削減以外にも工場のIoT化やテレワークなどのDX化なども含まれているため、無形固定資産への投資が不十分な場合、DX化が推進できない状態が続いてしまいます。
▷人材育成が進まない
日本の製造業は高い技術力を持っていますが、人材不足で技術の継承ができない状況にある点も大きな課題です。
経済産業省によれば、製造業において計画的なOJTやOFF-JTを実施した企業の割合は新型コロナウイルスの影響もあり、2019年から2020年にかけて低下しました。2022年度時点では再び上昇傾向にあるものの、2019年以前の数値には及んでいません。また、人材育成の問題点の内訳は「指導する人材が不足している」が6割程度となっており、半数以上の企業が人材育成のための人材が不足していると回答しています。
日本の製造業が高い技術力を持っていても、技術の継承ができなければ衰退してしまうため、早期に解決が必要な課題といえるでしょう。
製造業界におけるM&Aの現状と動向

製造業界のM&Aは、事業承継や生産性の効率化、販路の拡大など、様々な目的で行われます。
ここからは、製造業界におけるM&Aの動向を紹介します。
▷大手企業による中小企業買収M&Aが多い
製造業界でのM&Aは一般的に中小企業同士で行われるケースが少なく、大手企業の傘下に入るために実施されるケースが多いとされています。
このようなM&Aでは譲渡企業の経営が悪化していることが多く、事業整理やコストの削減などから会社や事業の譲渡が検討される傾向があります。
他方、譲受企業は業界の課題でもある人材の確保を目的としてM&Aを活用する傾向があります。
▷本業の変革・IT革新のための異業種M&Aが増加
製造業界では、多角的な経営から中核となる事業に集中する企業も増えており、M&Aを活用して中核事業以外を手放すことや、中核事業に関連する事業を取り込むケースが増えています。
また、他業種同様に製造業でもDX化やIT化への対応が迫られている傾向があります。自社でIT人材の教育を進めている企業もありますが、IT人材の教育については量・質共に不足感を持つ企業も多いのが実情です。
事実、経済産業省によると「IT人材が大幅に不足している」と回答した企業は全体の約4割に達しています。このようなIT人材の確保や最新技術への対応を目的に、M&AによってIT企業を買収するケースも増えています。
▷後継者不足解消のためのM&Aが増加傾向
休廃業・解散の件数は、製造業を含めて産業全体でも、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。
要因は、主に後継者不足です。また、事業承継ができずに廃業してしまうと、既存の従業員だけではなく取引先にも大きな影響を与えてしまいます。
M&Aによる事業継承は、後継者不足を解消する手段の1つとして活用されており、製造業に限らず増加傾向にあります。
製造業でM&Aを活用するメリット
製造業でM&Aを活用するメリットはいくつか挙げられ、さらに、譲受企業と譲渡企業によっても異なります。以下では譲受企業と譲渡企業それぞれのメリットを紹介します。
▷譲受企業のメリット
M&Aによる譲受企業の主なメリットには、以下のようなものがあります。
・技術と人材の確保が期待できる
・原材料の仕入れや機械などのリソースを活用できる
・事業の内製化が可能になる
それぞれ解説します。
技術と人材の確保が期待できる
製造業界では高齢の働き手、いわゆる団塊世代が退職したことで、人材の確保や育成が問題となっています。
人材の確保や育成には時間もコストもかかりますが、M&Aを行うことによって、譲受企業は譲渡企業の技術と人材の確保が可能になります。そのため、一からの創業であればかかるはずの「時間」や「コスト」を大幅に削減でき、技術力や人材の素早い確保につながります。
原材料の仕入れや機械などのリソースを活用できる
M&Aを行うと、譲受企業は売却条件によって譲渡企業の取引先や設備も譲り受けることができます。
製造業は、一から原材料の仕入れ先を探し設備も整える場合、多大なコストや時間がかかりますが、M&Aを活用すれば、事業に必要な取引先や設備などの経営資源をまとめて獲得することが可能となるため、自社の成長や新規事業の立ち上げにかかるコストや時間の削減が期待できるでしょう。
事業の内製化が可能になる
製造業界では、業務の効率化やコストの削減を目的として内製化(自社グループで一貫した製造を行うビジネスモデル)に取り組む企業も多くあります。
内製化には自社が持ち得ない技術やノウハウが必要となることが多く、対応できる人材が必要になります。譲受企業は、M&Aによって譲渡企業の技術やノウハウを得ることができ、効率的な内製化が可能になるでしょう。
▷譲渡企業のメリット
M&Aによる譲渡企業の主なメリットには、以下のようなものがあります。
・廃業コストを削減できる
・譲渡益を獲得できる
・後継者がいなくても事業を承継できる
こちらもそれぞれ解説します。
廃業コストを削減できる
製造業に携わる企業の大半が製造や修理で使用する何かしらの設備を所有しています。
そのため、廃業する際にも設備を処分するための費用など多額の費用が必要になります。設備の処分にかかる費用は自費で行いますが、M&Aで会社や事業を譲渡できれば、設備もそのまま譲渡できる可能性があるため、廃業にかかるコストを削減できるでしょう。
譲渡益を獲得できる
製造業を営んでいる企業は、負債があったりキャッシュが不足していたりするケースが珍しくないため、そのまま廃業してしまうと何も残らないという場合も多くあります。
しかし、M&Aによって会社や事業を譲渡できれば、経営者は譲渡益を獲得できるため、新規事業の立ち上げやセカンドライフの資金にも充てることができます。
後継者がいなくても事業を承継できる
製造業を営む経営者の中には、後継者が決まらずに事業承継ができないという悩みを抱える方が大勢います。そこでM&Aを活用すると第三者への事業譲渡によって、後継者がいなくても事業承継が可能になります。
M&Aによって第三者に事業を承継すれば会社や事業自体は存続できるため、既存従業員の雇用を守れたり取引先に影響を与えなくて済んだりするだけではなく、主に地方については地域のインフラを守ることにも繋がります。
また、製造業のM&Aでは譲受企業が大手になるケースがほとんどのため、シナジー効果も期待でき、自社の大幅な成長も期待できるでしょう。
製造業のM&Aに用いられる手法
製造業のM&Aに用いられる手法としては、次の2つが一般的です。
| 製造業の主なM&Aスキーム ・事業譲渡 ・株式譲渡 |
事業譲渡は選択的譲渡の手法です。譲渡する事業や資産、許認可などを選択し、それぞれにおいて条件交渉や手続きが必要になります。譲渡したい事業や資産が決まっている場合は、事業譲渡が適しているといえるでしょう。
他方、株式譲渡は企業体として包括的に譲渡する手法です。事業や資産などにおいて個々に契約を締結する必要がないため、手続きが比較的簡便です。しかし、簿外債務などの隠れた負債や法的問題に発展する取引なども全て譲渡するため、事業譲渡と比較すると、譲受企業にとってリスクの大きい手法といえます。
また、事業譲渡・株式譲渡についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
▷関連記事:「事業譲渡とは?株式譲渡との違いやメリット・デメリットを徹底解説」
▷関連記事:「株式譲渡とは?他のM&A手法との違いや手続きの流れ、税金について解説」
製造業のM&Aの費用相場
M&Aを行う際は、企業価値を算定する必要があります。
企業評価は、一般的にを「時価純資産額+営業利益×2~5年分」で概算します。譲渡・譲受の検討をする際は、一度概算してみましょう。
ただし、実際にM&Aを検討する際には、上記の企業価値算定についてもM&A仲介会社など専門家に依頼することが一般的です。特に、M&A仲介会社にサポートを依頼すれば譲渡先・譲渡先の紹介から具体的な交渉、契約締結までワンストップで対応してくれるため、本業に集中しつつM&Aを進められます。
M&A仲介会社に依頼する場合は、手数料が必要です。手数料には相談料や着手金などが含まれますが、その中でも多額を占めるのが成功報酬です。
成功報酬は、レーマン方式で計算することが一般的とされています。レーマン方式の計算方法(一般的な料率)については以下をご覧ください。
| 取引金額 | 料率 |
| 5億円まで | 5% |
| 5~10億円まで | 4% |
| 10~50億円まで | 3% |
| 50~100億円まで | 2% |
| 100億円超 | 1% |
M&A仲介会社によっては報酬を求める割合や基準が一般的なレーマン方式と異なることや、譲渡価額が低いときは最低報酬が決められている場合もあります。
製造業M&Aの3つの事例
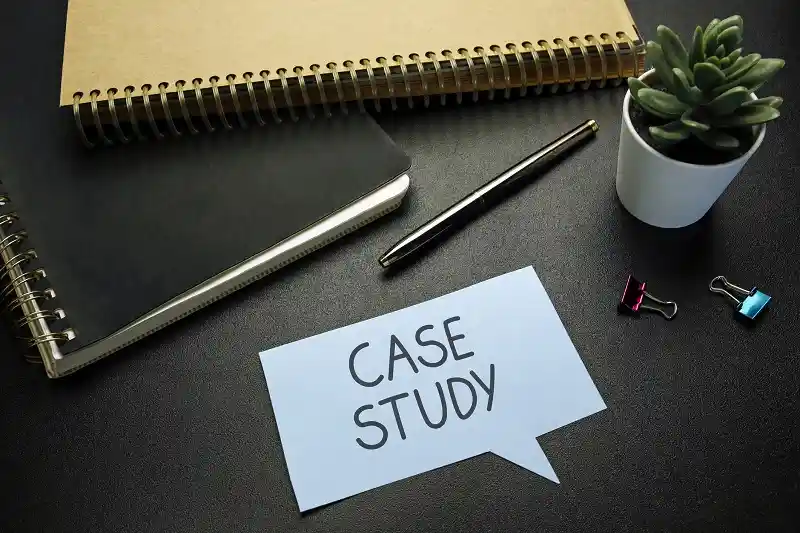
製造業でM&Aが実施された事例を3つ紹介します。
実際のM&Aの事例を見ることで、目的や活用方法が把握できるため、確認しておきましょう。
▷M&A事例①:日本電産による工作機器メーカーOKKの買収
2022年2月、精密小型モータや車載及び家電・商業・産業用モータなどを主軸とする日本電産株式会社が創業100年の老舗工作機器メーカーのOKK株式会社を買収し、傘下に加えました。買収額は約54億円とされています。
日本電産は2021年の8月に三菱重工工作機械(現日本電産マシンツール)を買収しており、OKKを傘下に加えることで、OKKの強みである汎用性の高いマシニングセンタと、日本電産マシンツールの門形五面加工機や横中ぐりフライス盤などの大型機を組み合わせ、幅広いサイズの加工ニーズに対応したいとしています。
この買収によって、日本電産グループと OKK のそれぞれが所持する技術力やブランド力、顧客基盤を活用し、グローバルベースでの工作機械市場の発展が期待されています。
▷M&A事例②:テクノホライゾン・ホールディングスによるブルービジョンの買収
2020年5月、テクノホライゾン・ホールディングス株式会社は、連結子会社である株式会社タイテックによる株式会社ブルービジョンの発行株式のうち1,460株(81.11%)を取得しました。
ブルービジョンは光学機器及び関連機器の企画・設計・製造・販売を手がける企業です。テクノホライゾン・ホールディングス株式会社はブルービジョンをグループ内に取り込むことで、シナジー効果を高め、魅力ある製品の提供を目指すとしています。
▷M&A事例③:シェアリングテクノロジーによる電子プリント工業の買収
2018年4月、シェアリングテクノロジー株式会社は電子プリント工業株式会社の株式を100%取得し、完全子会社化しています。取引価額は約5.9億円です。
シェアリングテクノロジーは、シロアリ100番やフランチャイズの窓口など、一般家庭で生じる生活トラブル関連サービスを対象としたWebサービスを展開するIT業界の企業です。
他方、電子プリント工業は白物家電や照明器具などに使われるプリント配線板の製造・販売事業を行う企業です。
シェアリングテクノロジー株式会社は、大手電機メーカーを取引先に持っている電子プリント工業をグループに取り込むことで企業価値拡大を図りたいとしています。
製造業でM&Aを成功させるためのポイントと注意点
M&Aを成功させるためには、いくつかポイントがあります。
ここでは、製造業ならではの成功のポイントを譲受企業・譲渡企業別に紹介します。
▷譲受企業のポイントと注意点
まずは、譲受企業の目線で押さえておきたいポイントと注意点を紹介します。
ポイント①買収後の計画を立てておく
M&Aを行う際は、買収する前に買収後の計画を立てておくことが必要です。経営方針や規模、何を引き継ぎ、何を変更するのか具体的に決めておきましょう。
特に注意したいのが、法律や権利上での制約を受ける可能性についてです。場合によっては事業をそのまま引き継げないだけでなく、新たに許認可を取得する必要が生じることもあります。
ポイント②デューディリジェンスは厳密に行う
M&Aでは、譲受企業が譲渡企業に対してデューディリジェンスを実施しますが、製造業はサプライチェーンやDX化に伴う設備投資など、一般的な企業にはない特徴があります。
そのため、デューディリジェンスが不十分な場合は、M&A後に赤字販売が発覚したり想定外の設備投資が必要になったりする可能性があることに注意が必要です。製造業に限った注意点ではありませんが、M&Aを実施する際はデューディリジェンスを厳密に行い、事前に注意点を理解しておくようにしましょう。
▷関連記事:「M&Aで重要なデューディリジェンス(DD)とは?種類や手順・費用や注意点を解説」
注意点①M&A後に巨額の投資が必要な場合があることに注意する
M&Aを検討している譲渡企業では、設備投資を実施していないケースが少なくありません。そのため、M&A後、譲受企業は譲渡企業に対して生産性の向上やDX化の推進など、最適化に向けた巨額の設備投資が必要になる可能性を考えておきましょう。
ちなみに、製造業は一から設備や人材を集める場合、時間もコストもかかります。そのため、M&A後に設備投資が必要になったとしても、一からの創業と比べると時間とコストを削減できる可能性が高く、M&Aを実施する企業が多いと考えられます。
注意点②取引先や従業員を引き継げるとは限らない
M&Aを参考行うからといって、譲渡企業の取引先や従業員を必ずしも想定どおり引き継げるとは限りません。従業員を引き継げない場合、人手不足に陥るだけでなく技術の継承も難しくなり、製品のクオリティが著しく低下する恐れがあります。
▷譲渡企業のポイントと注意点
次に、譲渡企業の目線でポイントと注意点を紹介します。
ポイント①自社の強みを正確に把握してアピールする
M&Aを行う際は、自社の強みを正確に把握しアピールできるように準備する必要があります。どのようにアピールするかによって譲渡価額が大きく左右され、獲得できる利益も大きく変わってきます。
ポイント②製造業M&Aに強い専門家のアドバイスも検討する
M&Aは専門的な知識が必要となるため、実施する際はM&Aアドバイザーなどの専門家に相談するのが一般的ですが、専門家にも得意な分野と不得意な分野があります。
特に、製造業は一般的なM&Aと異なる面があるため、希望の譲受企業を見つけて正しい価額で譲渡するためにも、製造業界に強い専門家に相談すると良いでしょう。
注意点①取引先との関係が悪化する可能性がある
企業は人対人で取引が成り立っているため、経営者が変わることで取引先との関係が悪化する可能性もあります。特に中小企業では、経営者と取引先の個人的なつながりが重視される傾向にあるため、引継ぎなどを十分に行う必要があります。
注意点②技術・ノウハウが失われる可能性がある
M&A実施後に経営方針や業務内容、社風が変化するケースも想定されます。新しい経営方針や社風に合わず、既存従業員が離脱するリスクもあるでしょう。また、引継ぎ対応の不足によって今まで培ってきた会社の技術やノウハウが失われる可能性もあります。
まとめ
製造業は日本経済を支える中心産業ですが、多くの課題を抱えています。M&Aを活用することで、譲受企業と譲渡企業の双方にメリットがあり、製造業が抱える課題の解決にも繋がるため、M&Aを活用することはとても有効的です。
ただし、M&Aを成功させるためには、製造業ならではのポイントを把握する必要があります。M&Aは専門的な知識が必要になるため、M&Aを検討する際は製造業界に強い専門家に相談するのがおすすめです。
