
農業を営んでいる方の中には、経営の未来を考え事業承継を検討している方も多いのではないでしょうか。
農業の事業承継を行う際は、農地や設備などの事業用資産、栽培技術や飼養管理などのノウハウや経験を後継者に引き継ぐ必要があります。後継者の選定から承継が完了するまでには相応の年数がかかるため、計画的な実行が大切です。
本記事では、農業における事業承継の現状や承継で引き継がれるもの、承継の種類とメリット・デメリット、承継の流れを紹介します。また、後継者問題の解決策となる農業M&Aについて事業承継を成功させるポイントも解説します。事業承継をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
年間3,000回の面談をこなすアドバイザーの声をもとにまとめた、譲渡を検討する前に知っておくべき5つの要件を解説。

・企業価値の算出方法
・M&Aの進め方や全体の流れ
・成約までに必要な期間
・M&Aに向けて事前に準備すべきこと
会社を譲渡する前に考えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。M&Aの検討をこれから始める方は是非ご一読ください!
目次
農業における事業承継が注目される背景
近年、農業業界では高齢化が進み、後継者不足が深刻化しています。事業承継の希望者を探すことが難しく、困難な状況に陥っている方も多いのではないでしょうか。
このような状況の中、政府は国内の農業を保護して事業承継を促す観点から、法人が農業に参入しやすい環境づくりを進めています。
▷高齢化による後継者不足
農林水産省の「農業労働力に関する統計」によると、基幹的農業従事者(仕事として主に自営農業に従事している方)の人数と平均年齢は、下記のように推移しています。
| 平成27(2015)年 | 平成28(2016)年 | 平成29(2017)年 | 平成30(2018)年 | 平成31(2019)年 | 令和2(2020)年 | 令和3(2016)年 | 令和4(2022)年 | 令和5(2023)年 | 令和6(2024)年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹的農業従事者 | 175.7万人 | 158.6万人 | 150.7万人 | 145.1万人 | 140.4万人 | 136.3万人 | 130.2万人 | 122.6万人 | 116.4万人 | 111.4万人 |
| うち65歳以上 | 114.0万人 | 103.1万人 | 100.1万人 | 98.7万人 | 97.9万人 | 94.9万人 | 90.5万人 | 86.0万人 | 82.3万人 | 79.9万人 |
| 平均年齢 | 67.1歳 | 66.8歳 | 66.6歳 | 66.6歳 | 66.8歳 | 67.8歳 | 67.9歳 | 68.4歳 | 68.7歳 | 69.2歳 |
表を見ると、直近10年間の基幹的農業従事者の平均年齢は66~69歳を推移しており、その多くが65歳以上の高齢者の方で占められていることがわかります。
一般的な企業であれば退職後の年齢に相当する方が、国内の農業を主として支えている状況です。
このように農業従事者の高齢化が進む中、後継者確保の問題が顕在化しています。農業センサス(2020年度)によれば、全国の1,075,705の農業経営体のうち、約7割の764,367の経営体が5年以内に引き継げる後継者を確保できていません。農業を営む多くの方が、後継者を見つけられていない状況があります。
▷改正農地法による法人の参入
農業における後継者確保の問題を受け、政府は様々な対策を実施してきました。その1つが、農地法の改正による法人の参入促進です。
以下に、近年実施された農地法の改正内容をまとめました。
・平成21(2009)年農地法改正:農地の権利取得や農地の貸借、農業生産法人要件などが見直された
・平成27(2015)年農地法改正:農地を所有できる法人の要件などが見直された
・令和元(2019)年農地法改正:農地集積における支援や事務手続きの簡素化などが行われた
農地法は、農業を保護するために農地の所有や転用、売買などに規制を設けた法律です。しかし、後継者確保が困難な昨今では規制が足かせとなるケースもありました。
平成21(2009)年の農地法改正では、改正後の約3年6ヶ月で株式会社やNPO法人などの農業参入数が改正前の約5倍のペースで増加しています。また、農地法改正により、令和5(2023)年4月1日に「下限面積要件」が撤廃されました。これらの農地法改正などが実施された結果、近年では一般法人の農業参入が積極的に行われています。
農業における事業承継で引き継がれるもの
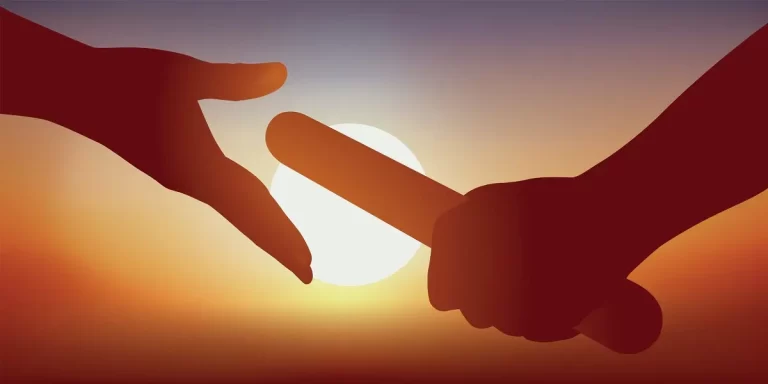
農業の事業承継では、主に以下の3つのものが引き継がれます。
・事業(経営)の承継
・財産の承継
・無形財産の承継
それぞれの項目を以下で詳しく説明します。
▷事業(経営)の承継
事業(経営)の承継とは、後継者に経営権を承継することです。
農業は、天候に合わせた作物栽培の技術や経験、地域住民との関わりなどに依存する部分が大きく多様なスキルが必要になるため、適切な後継者探しが重要です。
後継者への承継方法には、親族内承継や親族外承継(従業員など)、第三者承継(M&A)などがあります。各承継の詳細は後述するので、そちらもご参照ください。
▷財産の承継
財産の承継は、事業用資産や資金など有形の資産を承継することです。
農業の場合では、農地や耕作機械、牛や豚などの動物、ミカンやぶどうなどの樹木、運転資金や借入金などがあります。なお、自宅と農業に利用している設備が一体のケースでは、事業用資産と個人資産の区分に注意が必要です。
また、事業を事前に法人化し、事業用資産や資金を個人資産と分けてから事業を承継する方法もあります。
▷無形財産の承継
無形財産の承継とは、貸借対照表に記載されている資産以外の無形資産を承継することです。
具体的には、経営理念や技術・ノウハウ、経営者が培ってきた信用、ブランドや商標などの知的財産などが挙げられます。
農業の場合は、作物の栽培方法や飼養管理のノウハウ、生産物の販路などが知的資産の具体例です。その他、生産から販売までのビジネスモデル、農家としての歴史や地域との関わりなど多くの目に見えない資産があります。
承継前に知的資産を整理し、後継者との対話を通じて引き継ぐことが大切です。
農業における事業承継の種類とメリット・デメリット

農業における事業承継の種類は、承継の対象によって大きく3つに分類されます。
・親族内承継
・親族外承継(従業員などへの承継)
・第三者承継(M&A)
農業センサス2020年によると、「5年以内に農業を引き継ぐ後継者を確保している」と回答した262,278件の経営体のうち、250,158件は親族への引き継ぎです。
また、8,712件は親族以外の経営内部(従業員)への引き継ぎ、3,408件は第三者への引き継ぎであり、農業の事業承継は親族間で実施されるケースが多く見受けられます。
それぞれの承継がどのような内容か、メリットやデメリットとともに解説します。
▷親族内承継
親族内承継は、経営者の子をはじめとする親族に事業を承継することを指します。子以外では、兄弟の子や娘婿なども親族内承継に含まれます。
以下では、親族内で農業の事業承継を実施するメリットとデメリットを紹介します。
親族内承継のメリットとデメリット
下表に、親族内承継の主なメリットおよびデメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 関係者の理解を得られやすい 準備期間を確保できる 幼少期から農業に触れているケースがある | 相続人が複数存在する場合、資産の分配が難しい 親族でも家業を継ぐ意思があるとは限らない |
親族内承継のメリットは、経営者の子など親族が事業を承継するため、従業員や取引先・地域住民など関係者の理解を得られやすい点です。
また、小さい頃から農作業を手伝っている方も多く、農業に対する理解があることも利点でしょう。
一方、事業用資産と個人資産の分離があいまいな場合も見受けられます。相続人が複数存在する場合、事業に必要な資産を後継者に集中して承継することが難しいケースもあります。
▷親族外承継(従業員などへの承継等)
親族外承継は、役員や従業員・共同創業者・新規就農希望者など親族以外に事業を承継することです。
親族以外に事業を承継する際には、メリットとデメリットがあります。それぞれについて正確に把握しておきましょう。
親族外承継のメリットとデメリット
下表に、親族外承継(従業員などへの承継)の主なメリットとデメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 親族内に後継者がいない場合でも後継者を確保できる 農業に長年従事し、技術やノウハウを持った後継者を選びやすい | 後継者に資金力が必要となる 親族内承継とくらべ、関係者の理解を得られにくい |
親族外承継の大きなメリットは、親族内に後継者がいない場合でも事業を継続できる点です。先祖から受け継いできた家業を辞めることなく、次の世代へと引き継げます。
ただし、農業の事業承継では農地や耕作機械など高額な資産の承継が生じる場合が多く、承継する際には後継者に資金力が必要とされる点を把握しておきましょう。
▷第三者承継(M&A)
第三者承継とは、親族外承継の中でも、従業員以外(外部企業など)に事業を承継することです。第三者承継では、事業譲渡や株式譲渡(株式会社の場合)によるM&Aや外部人材の招聘などの方法があります。
家族経営の農業では従業員を雇っていない場合も多く、親族以外の後継者確保に困難を極めるケースが多いため、近年、第三者承継が後継者確保の1つの手段として注目されています。
以下では、第三者承継のメリット・デメリットを紹介します。
第三者承継のメリットとデメリット
下表に、第三者承継の主なメリットとデメリットをまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 親族や従業員に後継者がいない場合でも広く後継者を求めることができる 事業を存続できる 事業売却による利益を得られる | 希望する条件に合致する後継者の確保に時間がかかる 後継者が農業関係者であるとは限らない |
第三者承継のメリットは、広く後継者を求められる点です。事業存続のための選択肢が増え、廃業を避けられる可能性が増えます。また、M&Aによって事業を売却できれば、売却益を得られる場合もあります。
一方、第三者承継は、親族内承継や親族外承継に比べて自分が望む条件を持つ後継者が見つかるまでに時間がかかる点がデメリットです。新規就農希望者を受け入れる場合には、農業の基礎から育成する必要もあります。
農業における事業承継の流れ
事業承継は、現経営者にとっても後継者にとっても生涯に1度経験するかしないかという重要なイベントです。事業承継を成功させるためには、どのように進めるべきか正しく把握しておく必要があります。
以下は、事業承継の大まかな流れです。
1. 準備段階:事業承継の必要性を確認し、経営状況・資産を把握したうえで、後継者の選定・育成を実施する
2. 計画段階:事業承継計画を策定する
3. 実行段階:事業承継計画を実行し、承継後にも伴走して経営の発展を支援する
⽣産技術・ノウハウの承継や後継者の育成は、短期間では実現できません。そのため、準備段階に充分な時間を確保することが重要です。「同業者とのネットワーク」「顧客との関係」など、財務諸表を眺めるだけでは見えない要素もあります。マニュアルなどの文書を作成し、後継者がスムーズに事業を承継できる状況を構築しましょう。
後継者を探す際は、まずは親族や従業員などに声をかけ、適任者がいない場合は就農希望者を新規に雇用することも検討しましょう。仕⼊先・販売先や地元の農業関係団体などから適任者を探したり、第三者への事業承継(M&A)を実施したりすることも選択肢の1つです。
後継者が見つかったら、現経営者と後継者が一緒にそれぞれのライフプランを踏まえて継続的に対話しながら、事業承継計画を策定しましょう。必要に応じて計画を修正したり、再合意を繰り返したりしながら、ブラッシュアップしていきます。
計画が確定したら、農業経営に必要な資産や株式の譲渡(売却)などを実行する段階に移行します。トラブルを未然に防⽌するために、このタイミングで「経営承継契約書」や「株式譲渡契約書」などを作成・交付する必要があります。経営権や資産の移譲が完了した後も、しばらくは先代経営者が伴走し、PDCAサイクルを回して施策を修正・改善していくのがおすすめです。
後継者不足を解消する農業M&A
後継者確保に多くの農家が苦労する中、近年では第三者に事業を承継する農業M&Aが積極的に行われています。
以下、農業M&Aの事例やその他の第三者への事業承継の例を紹介します。
▷農業M&Aの事例
2020年1月、鹿児島市に本社を置き業務用総合食品卸業を営む西原商会は、農業M&Aを実施しました。具体的には、グループ会社であるニシハラグリーンファームを介してニンジンやゴボウ、米などの栽培を手掛ける松本農園の全株式を取得しています。
西原商会は、松本農園の買収によって、生産から販売までの一貫したサービスの提供が可能となりました。
また、2020年3月には、大和証券グループの子会社である大和フード&アグリ株式会社も農業M&Aを実施しています。具体的には、山形県で低コスト耐候性ハウスを使用したトマト栽培を営む株式会社平洲農園に資本参加しました。目的は、トマト生産ビジネスへの参入です。
このように、多くの企業が農業にビジネスとしての魅力を感じてM&Aを行い、農業・食料分野への新規参入を図っています。
▷新規就農者への事業承継や他の農業法人との統合というケースも
第三者への事業承継では、新規就農希望者を募り承継を実施するケースもあります。
外部から新規就農希望者を招き入れ、研修生として数年間雇用した後、事業を承継する方法です。資産の継承には農地や機械を使用貸借契約する方法もあり、新規就農者の費用面での負担にも配慮できます。
また、法人化している場合は、同じ地域で法人として農業を営んでいる方のグループ法人になることも1つの手段です。後継者となる親族がいない場合でも、家業を廃業することなく事業継続が可能です。
農業における事業承継を成功させるポイント
近年、国は農業の事業承継に対して様々な支援策を実施しています。政府支援策の積極的な活用は農業における事業承継を成功させるうえで重要なポイントです。
また、後継者が見つからない場合はマッチングサイトの活用や、農業研修を実施して参加者に声をかけることも有効な手段です。
▷政府支援策を活用する
国が行っている支援策には以下のようなものがあります。
・農地に関する納税猶予制度や事業承継税制など、税に関する支援策
・経営継承・発展等支援事業の実施
・農業経営・就農支援センターの整備
・経営継承に関するパンフレットの発行
農地に関する納税猶予制度とは、農地を全て後継者に贈与した場合に贈与税の納税が猶予される制度です。
また、事業承継税制を活用すると、事業用資産の承継に課される贈与税・相続税が猶予または免除されます。
その他、農林水産省では、経営継承・発展等支援事業の実施や農業経営・就農支援センターの整備など、多彩な支援事業を用意しています。
経営継承・発展等支援事業とは、後継者が経営継承後の経営発展に関する計画を策定し、同計画に基づく取り組みを実施する場合に必要な経費の支援を受けられる制度です。令和3(2021)年度から実施されています。なお、支援金額の上限は100万円で、国・市町村がそれぞれ1/2を負担する仕組みです。
農業経営・就農支援センターでは、農業経営の改善・法人化・円滑な経営継承などの経営上の課題に対し、伴走型支援を実施しています。各都道府県にセンターが設置されており、経営診断や専門家の派遣・巡回指導などを受けられます。
▷マッチングサイトを活用する
マッチングサイトとはインターネットを活用し、オンライン上で事業の譲渡希望者と譲受希望者をマッチングするWebサイトです。
農業分野では、「AgriTouch」という農業専門の事業承継プラットフォームがあります。後継者を探している方と農業に携わりたい個人・企業をマッチングするサービスです。親族・従業員などが後継者として適さない場合に、外部から後継者候補を探すために役立ちます。
▷農業研修を実施し、参加者に声をかける
農業研修を実施することも、後継者探しに役立ちます。研修の参加者は、農業に対する興味を有する人物が多いため、事業の承継を希望する人物と出会えるかもしれません。
例えば、北海道三笠市でミニトマトやメロンなどを生産している「のみやまファーム」の現経営者は、農業研修の際に声をかけられたことがきっかけで事業を承継しました。栽培技術や水の確保など、農業に必要なノウハウを先代から学び、事業を発展させています。
▷専門家に相談する
農業の事業を承継する場合には、後継者探しの他、資産の承継に関する税の問題や法務・会計などの専門的な知識も必要です。
事業承継やM&Aの経験が豊富なM&Aアドバイザーが在籍するM&A仲介会社へ依頼すれば、事業承継の手続きをスムーズに実施できます。
まとめ
近年、農業を営む方の高齢化が進行し、後継者不足の問題が顕在化しています。そんな中で国は農地法改正など制度面の整備を進めており、法人が農業経営に参入しやすい環境作りを行っています。
事業承継には親族内承継や親族外承継、第三者承継(M&A)などの種類があり、事業用資産や資金などの有形資産や経営理念やノウハウなどの知的資産を承継します。
事業承継は、短期間では実現できません。準備に充分な時間を確保し、先代経営者と後継者が協力して事業承継計画の内容をブラッシュアップしながら進めていく必要があります。また、政府の支援制度(経営継承・発展等支援事業など)を活用することも併せて検討できると良いでしょう。
後継者の確保を含め、将来を見据えた事業承継が重要です。
農業の事業承継で不明な点がある場合は、専門家への相談も1つの手段です。fundbookでは、事業承継の経験が豊富なアドバイザーが、農業経営者の方に寄り添ったサポートを提供します。
ぜひお気軽に弊社までご相談ください。
