自社を譲渡したい方まずはM&Aアドバイザーに無料相談
相談料、着手金、企業価値算定無料、
お気軽にお問い合わせください
他社を譲受したい方まずはM&A案件情報を確認
fundbookが厳選した
優良譲渡M&A案件が検索できます

医師の高野英男氏が1980年に福島県双葉郡広野町で創設した「医療法人社団養高会 高野病院」。眼下に海を望む自然豊かなこの場所で、地域の皆様に寄り添った医療を提供しています。英男氏の娘・高野己保氏(以下、高野氏)も、事務長として職員や患者を支えてきました。
そんな高野病院の日常が、2011年3月の東日本大震災で一変。震災直後のライフラインの寸断はおろか、原発事故の避難指示区域から程近いために職員が減少し、さらには広域な双葉郡で高野病院だけが診療を続ける事態になりました。ただ一人の常勤医として働き続けた英男氏も心労が重なり、2016年末に急逝。その1カ月前に理事長を継いでいた高野氏にとって、まさにそこからも医師探しやコロナ禍などで苦難が絶えなかったと言います。
病院を残すために奔走し続けて7年。医師であり、医療機関の経営改善でも実績の豊富な小澤典行氏と出会い、2023年11月に小澤氏が高野病院を承継。地域医療の拡充に向けた取り組みが、もうすでに始まっています。病院も地域も幸せになるM&Aの形とは――。高野氏と小澤氏にお話を伺いました。


高野氏:医師としての父は本当に尊敬すべき人でしたが、娘の私からすると、幼い頃から父と一緒に過ごした記憶がほとんどないほど、家族を二の次にしてまでも医師として生きてきた人でした。高野病院は私が中学生の頃に開業し、当時の私は多感な時期でしたから「何においても患者さんを優先させる父が、家族を放っておいてまでも守りたいものや、貫きたいものとは一体何なのだろう」と、最初はけんか腰で見るような興味があったんです。
30年ほど前に、初代の事務長が体調を崩されて代わりの人員が必要となり、それがきっかけで私が高野病院に入職することになりました。当初は時々来ては院長秘書や事務長の手伝いをしていましたが、次第にここでの仕事がメインとなり、2002年には事務長代理に就任し、その後2008年に事務長に就任しました。
高野氏:病院を創設した院長の娘が来るとなると、親の七光りと思われても仕方がないです。最初は事務を手伝う程度でしたが、急に事務長代理になって指示をする立場になったわけですから、それを面白く思わない人だって少なくありません。なので、まずはその人たちが一緒に仕事をしてくれるように働きかけようと心掛けてきました。
昼食後に職員が集まる休憩室に毎日出向き、最初は相手にしてもらえなかったものの、徐々に話してくれるようになり、1年も経たないうちに「早くおいで!」と言われるまでになりました。事務仕事は慣れればどうにかなりますが、やはり人との関係性を構築するまでが一番大変でした。

高野氏:見えたというより諦めに近いような、「医師ってこうなのかな」と折れたんです。医師と事務長のそれぞれの立場から言い争いになることもありましたが、結局のところ、父の患者さんは常に寄り添ってもらえて幸せだったんだろうなと思います。
高野氏:急性期(発災から1週間程度)はとにかく、水、食料、燃料、電気など、生きるために必要なものを確保することに一番苦労しました。そんな誰もが大変なときでしたが、隣町のスーパーの社長が「食べ物を自由に持って行っていいよ」とお店の鍵を置いていってくださったり、近くのガソリンスタンドの所長も自家発電機用の軽油を使わせてくださったりと、皆様からの支援を受けられて本当に心強かったです。
また、自家発電機から異音がして、県の災害対策本部を通じて東北電力が持ってきてくれました。そのときの担当者が当院の状況を見て「こんなに頑張っている病院なのに、発電機を置いただけで去るわけにはいかない」と思ってくださったようで、3月の冷たい雨に濡れながら、1日がかりで遠くから電線をつないで電気を通してくださいました。
ほかにも、ガソリンが不足して職員が移動できないなか、当院の状況を知ったいわき市のガソリンスタンドの方から連絡をいただき、給油していただけたおかげで避難所に職員を迎えに行けましたし、そこで出会った新聞屋さんが「自分の親も入院中で、病院の大変さが分かるから」と、新聞を毎日渡してくださったんです。地域の皆様や初めて出会った方々にも助けられて、なおのこと病院を続けなければという気持ちになりましたね。
高野氏:2016年3月頃から、父に足腰の衰えや手の震えが見え始めたんです。検査をしても脳にはまったく異常がなく、今振り返ればフレイル(虚弱)状態だったと思いますが、やはり震災後の疲労が大きかったのでしょう。避難により職員が減ったため、長らく常勤医は父一人の状況が続き、いくら医師とはいえ、あの年代の人が続けられる仕事量ではありませんでしたから。
それで、何かあった場合でも必ず病院は残さないといけないと思い、半ば強引に父を説得して県に特例認可申請を出し、同年11月23日に事務長だった私が理事長に就任しました。その翌月に父が火災で急逝してしまったのですが、あのときに私が理事長に就任せずに事務長のまま病院を継続することになっていたら、もっと厳しい状況になっていただろうと考えると、父がいるうちに理事長をバトンタッチできていたことは不幸中の幸いだったと思います。
小澤氏:私は富山医科薬科大学(現:富山大学)医学部を卒業後、心臓カテーテル治療や遺伝子解析の研究にずっと従事してきましたが、ここ10年ほどはいくつかの病院で院長を務めながら、経営改善や病院経営の立て直しをすることに力を入れています。多いときにはグループで全国各地の5病院を同時に経営改善し、全ての黒字化に成功したという経験があります。
小澤氏:以前、医師として勤めていたときに、院長に就任するよう声が掛かったんです。ただ、当時の私はカテーテル治療に専念したく断っていたのですが、理事長からも「自分の好きなことだけをやっていてはいけない」と説得され、院長になることを決意しました。院長になるからには、やはり経営をしっかりできなければいけないだろうと思い、病院経営について徹底的に勉強するようになったのです。

小澤氏:医師というのは、本当にお金ではなく道徳心で動いているんです。だから、経営の観点にはなかなか立つことができないのです。私が心臓カテーテル治療をしていたときも当然、途中で終えるわけにはいかず、快方に向かうまで続けなければいけませんでした。ですが、そうすると保険がどんどん切られていき、赤字になってしまう。それを当然だと思っているのが、医療の現場です。いろんな院長と話していても、この状況を「仕方がない」と言うのですが、私は「仕方がないで済ますのではなく、工夫しなさい」と一貫して指導してきました。
決して、治療をするなと言っているわけではありません。病院の経営が成り立たなければ、治療することもできなくなると認識してほしいのです。私が臨床の現場に出たい本心をぐっと抑えてまで病院経営を専門とする道に進んだのも、やはり「患者を救う」という医師の満足のために、病院自体を危機にさらしてはいけないと強く思ったからです。医療の提供と経営のバランスを取るように工夫する意識を浸透させることが、今の課題だと思います。
高野氏:父がよく「病院がなければ患者さんが困る。患者さんがいなければ病院が困る。だから、お互い共存していかないといけない」と言っていたのですが、まさに小澤(現)理事長の仰る経営の観点を持つことにも通じると思います。ですが、そういう観点で医療を提供できる人は少ないようにも感じます。
高野氏:2022年3月頃から検討を始めました。コロナ禍の影響で赤字が続いてしまい、それでも病院を閉めるわけにはいかないという思いが一番にあったので、病院を残すためのいろんな選択肢を考えたんです。その一つにM&Aもありましたが、M&Aについて詳しく知らなかったので、当時の経営コンサルタント経由で仲介業者に相談しました。ところがその仲介業者の担当者と意見が合わずに頓挫してしまい、自己破産することも厭わないと腹をくくっていました。
そんなときに、偶然fundbookさんからM&Aの解説DVDを配布しているというご案内が届いたのです。日頃はそういった案内はほとんど目に留まらないのですが、病院を残す道に導かれていたのか、「申し込もう」と行動に移し、それを機にfundbookさんと連絡を取り合うようになりました。直前に一度M&Aが白紙になってもう懲りていたはずなのに、不思議なものです。
小澤氏:私が以前勤務していた病院グループは何度かM&Aを実施していたのですが、そこで身に染みて思ったのが、「規模を大きくすれば確かに安定はするものの、単なる陣取り合戦だけになって、M&A後の地域医療や病院職員を置き去りにしてはいけない」ということでした。なので、譲渡する側も譲受する側も、そして地域の皆様や患者さんも、全員がWin-Win-Winで幸せになるM&Aを目指し、自ら譲受に向けて動こうと考えました。
今、この高野病院の副理事長には、私と一緒に各地の病院を立て直してきた徳丸さんという方が就任しているのですが、Win-Win-Winの構想は彼とともに5年ほど前から温めてきていたもので、それが実現できる病院を探していたときに、高野病院と出会えたのです。
小澤氏:福島という土地は初めてだったので、はじめは「震災で大変だったんだろうな」くらいの想像しかできませんでした。そこで、高野顧問の奮闘がつづられた書籍(『福島原発22キロ 高野病院 奮戦記 がんばってるね!じむちょー』東京新聞出版局)を読んだところ、養高会の苦労や高野顧問の情熱がものすごく伝わってきたのです。私と徳丸さんが考えていた、地域を守り、病院を守っていくWin-Win-Winを叶える場所としてうってつけだと思い、「ぜひ、高野病院を承継したい!」と、声を掛けさせてもらいました。
小澤氏:高野顧問は書籍の通りのお人柄だなという印象でした。書籍には胸が詰まるほどの震災後の苦労が書かれていたのですが、それでも写真は全部笑顔だったんです。それは頑張って作った笑顔だったのかもしれませんが、あの苦労のなかで笑顔を出せるとは、なんて強い人なんだろうなと。誰にもできないことです。地域にそれだけ情熱を持っている人と一緒に仕事をしたいと心から思いましたし、今も当時の印象のままです。
高野氏:私自身はM&Aが成約すれば高野病院を去る覚悟をしていたのですが、後をお任せした際に病院はどうなるのかをとても気にしていました。M&A成約までは良いことを言っていても、後に職員の給与を下げたり、思わぬ方針転換をしたりするケースもゼロではないと思っていたので、最初にお会いした時点ではまだ100%信用していたわけではなかったんです。
ところが、小澤理事長が「病院の名前は変えません」と仰ってくださいまして。面談の場でそうはっきり断言してくださるということは、信用できるかもしれないと感じました。やっぱり父が高野病院にこだわってきて、私もこの名前を大事にしたいという思いがあったので、高野病院のまま承継してくださるのであれば嬉しいなと思いましたね。

小澤氏:やはり地元に高野病院があるということで、地域の皆様が安心感を持てているわけですから、高野病院として残さないといけません。なので変えることはありません。
高野氏:「自分が承継したからには、法人名や病院名を変えたい」と思う人も少なくないと考えていたんです。なので、高野病院として残すという決断は信用につながりましたし、同時に、「名前を変えたがらないなんて不思議だな」と思ったくらいでした。
高野氏:M&Aではかなり多くの資料を揃えて提出する必要があるので、一般的には3~4人が関与しながら進めることが多いそうですが、今回は私一人で進めていましたし、加えて子どもたちの引っ越しなど、病院と家庭の両方で色々な大仕事が重なったため、一時はかなりの激務をこなさないといけない状態でした。一方の小澤理事長はスピーディーに対応されていたようなので、まるでジェット機並みの進捗に目が回るようでしたが、小澤理事長の情熱や、こまめに連携してサポートしてくれたfundbookのアドバイザーさんのおかげで、成約まで進めてこられたと思っています。
小澤氏:高野病院は書類が非常にきれいにまとめられていました。いざM&Aをするとなったときに、必要な資料や証書が見つからないというケースも多いなか、創設から40年以上が経つにもかかわらずとてもスムーズに進められたのも、高野顧問が事務のトップとしても日頃から整理されてきたことに尽きると思います。
高野氏:成約直前のことですが、10月の最終調印の前日は本当に今までにないほど胃が痛くて、「私、こんなに根性がなかったのかな」と思いました。
そして11月にとうとう成約したときは、半々の気持ちが入り乱れていました。小澤理事長と徳丸副理事長は経営者としてすごく尊敬できる分、「私はこれができなかったんだ」と少し卑屈になるときもありましたし、反面では、父が亡くなってからの7年間、なんとか病院を残して引き継ぐことができたという安堵の気持ちが交互に押し寄せるような感じでした。
今はもう、高野病院がこれからも続いて、職員がハッピーでいてくれたらいいなと。その気持ちしかありません。
高野氏:当院にはお世話になった方々がたくさんいるので、さすがに急に「今日付で理事長を退任します」なんて不義理なことはできない、ということを小澤理事長にもご理解いただき、M&A成約の前から少し前から職員には伝えるようにしていました。職員だけには動揺させたくなく、一番先に伝えるべきだと思ったからです。
職員は高野病院が好きで働いていても、やはりそれぞれが自分の生活を守らないといけませんし、そういう人たちが集まって働いてくれていることを私たちは忘れてはいけません。職員からは高野病院がどうなるのか心配する声も寄せられましたが、個別に色々と聞きに来てもいいよと話しました。また、小澤理事長も心配事や疑問を解消できるように職員向けの説明会も開いてくださったので、すぐに落ち着けたのではないかと思います。
小澤氏:やはり震災を乗り越えてきたわけですから、この地域で暮らす方々は心が強く、職員の皆さんも自分をしっかり持って仕事をしてくれる人ばかりです。私の経験からも、理事長や院長が変わったり、何かが経営に入り込んできたりしたときは、もう皆が右往左往してしまうものですが、そんな事態にならず、きちんと統率を持って運営できているところに、高野病院の強さを感じます。
高野氏:M&A前から院長が変わらずにおりますので、病棟での連携はこれまで通りに取れていると思います。それもこれも、職員が不安なく仕事ができるよう、体制や環境を大きく変えずに努めてくださった小澤理事長のおかげです。

小澤氏:私は、最初から高野顧問には病院に残ってもらいたいと考えていました。Win-Win-Win構想でお話しした通り、地域の医療を守ることが重要なので、地域に一番精通する人がいなくなってしまっては、外から来た私たちだけでできることは何もないだろうと。それで、私たちからお願いして顧問を引き受けていただきました。
ただ、譲渡する側と譲受する側の心理はかなり違うと思うんです。高野顧問が成約時の気持ちを仰っていたように、自身が情熱を注いで守ってきた病院の経営権が移ったということなので、つらい思いもかなりあるだろうと考えると、顧問をお願いするのもすごく心苦しかったです。しかし、この病院は高野顧問がいなければきちんと維持できないでしょうし、やはり高野家が作ってきた病院ですから、理事長を務めてきた高野顧問にはしっかり見届けてほしいと、こちらの思いを伝えながらお願いさせてもらいました。
小澤氏:この地域の医療は、震災後に唯一診療を続けてきた高野病院が担っていくしかないと思っています。2018年に、救急医療を行うふたば救急総合医療センターが開設されましたが、双葉郡という広い土地で救急対応ができる医療機関はそこしかなく、1カ所で全域をカバーすることは不可能と言えます。
本来、高野病院は慢性期病院なのですが、震災からしばらくの混乱していた時期には、先代(英男様)がお一人で救急患者も受け入れていたそうです。今も地域のなかに困っている人たちがいるはずですから、当院も救急の入院施設になるしかないと考え、2023年1月から救急対応を再開しました。救急対応に必要な設備を整えるために開始したクラウドファンディングには、多くの方々から寄付をいただいています。
また、病院に通えない方々に必要な訪問診療も、この地域では不足していたため、2月から新たに開始しましたし、現在はさらにリハビリの強化にも取り組んでいます。高齢になったり、脳梗塞になったりした患者さんにとって、リハビリはとても大事になるので、リハビリ設備や専門人材を追加して、充実化を図っているところです。
高野氏:震災後、「何としてでも高野病院は残すんだ」という思いでここまでやってきたので、それはこれからも一貫して変わることはありません。ただ、父が「共存」と言っていたように、残るだけで役に立たない存在ではいけないのです。父が急逝してからは、医師を探すことさえすごく大変で、「この地域に高野病院は役に立っているのだろうか?」と考え込むときも多くありました。
今回、小澤理事長が来てくださったことで、高野病院がまた地域にきちんとお役に立てるようになってきたと実感していますし、以前の私たちではできなかったことを着実に進展させ、大きくしながら未来につないでくださっていると思い、ありがたい気持ちでいっぱいです。今後も、ここにあり続けながら地域に貢献していきたいという思いに尽きます。
小澤氏:維持することは大事ですが、私は、維持するために削減や効率化ばかりをやっていてはいけないと思うのです。救急、訪問診療、リハビリを強化しているように、外に向けて活動を広げていく“ポジティブな維持”もしていかなければいけません。この地域に本当に貢献できる病院として維持していくことは、高野顧問ともしっかりと意見が一致した私たちの目的であり、そこに向けて今の計画を拡大しています。ポジティブな考えのもとで維持し、進展していくことが、今後の高野病院の展開になります。
高野氏:私たちは東日本大震災と原発事故を経験しました。原発事故はとても異質な出来事だったにしても、その後各地でたくさんの災害が起きるたびに、経済的支援などといった、行政のあらゆる対応が不十分なままだと私は思うのです。もっと改善してもらうために、震災を経験した立場として何かをしないといけないという使命感から、震災についての講演を全国で続けてきました。ただ、2011年から日が経つごとに皆さんの興味が薄れてきたのか、依頼が少なくなったので、一度は講演をやめようと思った時期もありました。
しかし、2018年に北海道胆振東部地震が発生した際、避難所ではまだ段ボールしか敷けていなかったり、自家発電機がなかったりする様子を見て、やっぱり自分が経験したことは今後も続けていかなければいけないと痛切に感じたのです。災害発生直後は現地に出向いた医師や看護師によるケアが受けられると思いますが、彼らが引き上げた後に取り残された病院は、結局大きな困難に直面するわけです。実際、私たちがそうであったように。なので、私はあきらめずに伝え続けなきゃいけない――。そう思って、今も講演の依頼を受け続けています。
今後は理事長だったときよりも、もっと災害について勉強する時間などもきっと作れると思いますし、いざというときには現場でもっと動けるようになると思うんです。もちろん、災害が起きないことが一番の理想ですが、私の知識と経験と力を生かして困っている方々の助けになれるよう、これからも頑張っていきたいと思っています。

医療法人社団養高会 高野病院
顧問 高野 己保氏
今回のM&Aを経て、譲渡するにも経済的によほど限界を超えた状態では、成約までのハードルはすごく高くなっていただろうと思いました。譲受する側だけでなく、譲渡する側も当然一定のコストは必要になりますし、地域の皆様にとって必要で、今後も続いていくべき価値のある病院でなければ、承継者探しも難しかったのかもしれません。
一方で、いくら“事業承継”という名称で分かりやすく説明しても、「高野病院は一体どうなるんだ?」と心配される声を多くいただき、医療業界はとりわけM&Aに対するネガティブな先入観がまだまだ強く持たれていることも実感しました。
ですが、高野病院は確実に良い方向へ進展し始めています。当院のようなケースもあることや、小澤理事長のように全員の幸せを目指す考えを持って承継する方々もいることを、もっと広く認識していただけるようになれば嬉しく思います。
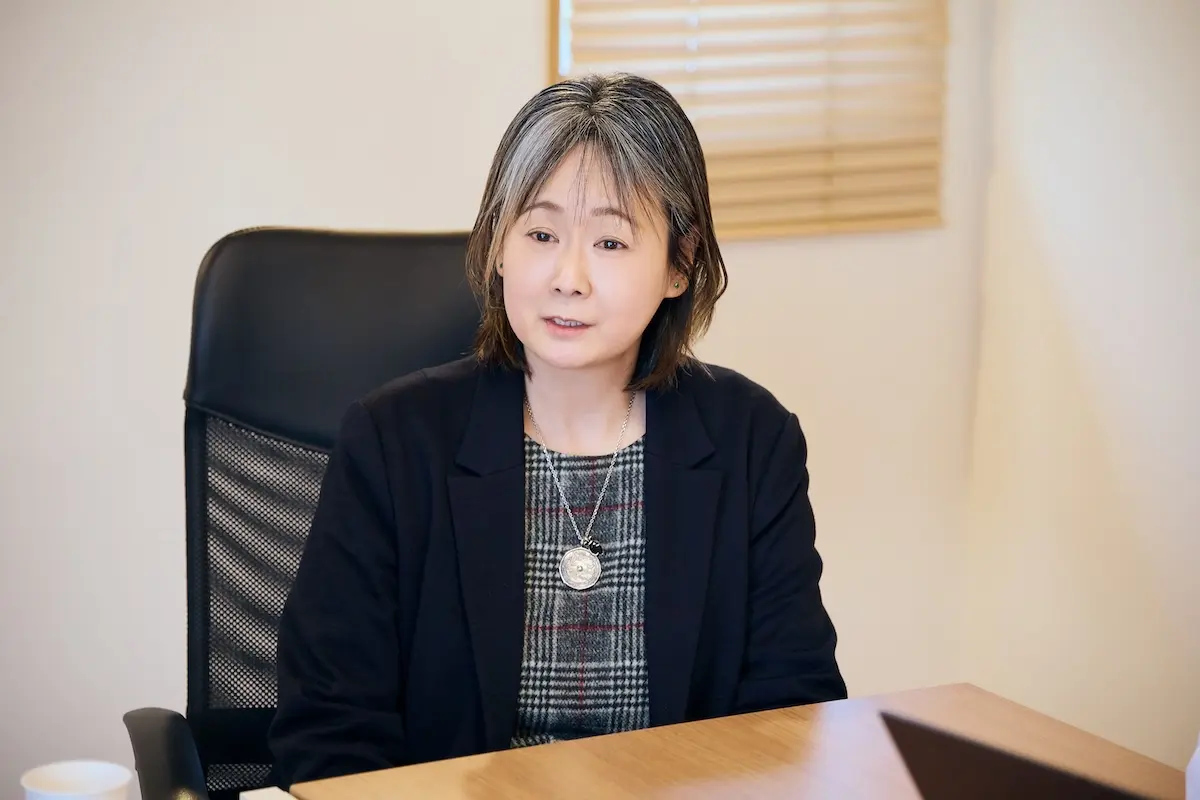
医療法人社団養高会 高野病院
理事長 小澤 典行氏
今、数多くの地方のクリニックや小規模の病院が後継者不在に悩んでおり、病院の存続が危機的な状況にあります。その解決策として、M&Aは今後ますます盛んになってくると思いますが、ただの陣取り合戦を目的に譲受するようではいけません。信頼の置かれている病院を、地域の方々が困らない形で承継するM&Aにしていかなければならないと思うのです。
また、最近は若くして医師を辞める人も珍しくなく、医療業界における引き継ぎの重要性について改めて考えさせられています。アーリーリタイアすること自体は、各々の価値観や人生観があるので肯定的に捉えていますが、医師というのは自身の人生と同様に、診ている患者さんの今後も大事に考えなければならない立場にあります。私はこれまでも患者さんが困らないよう手助けをしてきましたが、医師の引き継ぎや病院の承継は、患者さんを救うためにも意義が大きいものなのです。
そしてもう一つ、この高野病院のように、震災を経験した病院を後世にしっかり残していかなければいけません。当時、何が起きてどう対処したのか、その経験はここにいた職員にしか分からないことですし、私も承継するまではこれほどまでの苦難があったとは知り得ませんでした。病院を残し、啓発していかなければ、10年先も医療は進みません。有事の際にどう対処できるのか、それを示すことが私たちの大事な仕事であり、果たすべき責任だと思っています。

相談料、着手金、企業価値算定無料、
お気軽にお問い合わせください
fundbookが厳選した
優良譲渡M&A案件が検索できます
担当アドバイザー コメント
原発事故後、双葉郡の病院が次々と閉鎖する中、医療を提供し続けた唯一の病院が「高野病院」様です。この地から病院をなくすわけにはいかない、その一心で病院運営を行われてきました。そのような、地域医療の最後の砦ともいえる医療機関の事業承継に携われたことを光栄に思います。
昨年秋の事業承継後も、小澤理事長と高野顧問が協力して、病院運営をしておられます。2024年に入ってから、地域の医療ニーズに応えて、救急や訪問診療という新たな医療の提供も始め、新体制の下でも地域患者様の為に尽力しておられます。
二人三脚で、この地に必要な医療を提供し続けられることを影ながら応援しております。